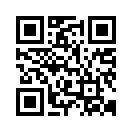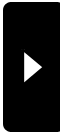› みどり児童館 › 事務室日記
› みどり児童館 › 事務室日記峰禎宏&平田義信
2018年07月06日
暴れ出しそうな有浦川
7月6日。大雨の影響で、学校は休校。従って、児童館も臨時休館となりました。あれよあれよと、上がっていく水位。先日、子供達に話した2012年7月13日の光景がフラッシュバックします。川沿いの道を乗り越え、迫る水に泣き出す子もいました。2時過ぎから満潮が来ました。3時過ぎからは水位が下がっていき、どうにか水は乗り越えずに済みました。大潮でなくて、本当に良かった。これからも大雨の警戒は続くと予想されています。このブログを挙げている間も、災害関連のメールが次々入ってきます。どうぞ、お気を付け下さい。
午後2時頃、児童館玄関より


2012年7月13日、同じ場所から



この頃は、まだ隣に小学校があり、想定外の事態で臨時休校ともなっていなかったため、児童館は元より学校の対応も慌ただしかったことを覚えています。児童館、学校、そして有浦川の境目が無くなってしまいました。
午後2時頃、児童館玄関より


2012年7月13日、同じ場所から



この頃は、まだ隣に小学校があり、想定外の事態で臨時休校ともなっていなかったため、児童館は元より学校の対応も慌ただしかったことを覚えています。児童館、学校、そして有浦川の境目が無くなってしまいました。
2018年06月28日
危険にも五分の魂
月に1度程度、児童館では火災避難訓練を行っています。子供達にとっては、保育園から繰り返されている訓練です。実際は慌てて冷静に考えられないもの。考えなくても安全が保たれるよう、体に覚え込ませるのも、繰り返す訓練の目的の一つ。子供達を襲うかもしれない災難は、火事だけとは限りません。地震、大雨、不審者、熱中症、感染症、そして場所的に原発事故。最近では危機感が薄れてきましたが、ミサイル攻撃もそうです。どんなに想像を巡らせても、その死角を縫って襲ってくるのが災害。そう考えると、想像力を鍛えることが、何よりの防災、危機管理につながるのかもしれません。このところ、不審者、ブロック塀など思いも寄らない、本来なら気にしないでも済むような場面で子供達が犠牲、または危険にさらされています。かといって、注意するポイントばかりを挙げてはキリがありません。不安で気もそぞろになり、帰って災いのつけいる隙を与えかねません。油断は心の余裕にもつながり、想像を自由にします。油断できるポイントを再点検し、不足なら補うことを始めないといけないような気がします。そして、危険を無理矢理排除したり、無視するのでなく、存在を認め、最小限の被害で済むよう、大人はもちろん、子どもも一緒に、危険との付き合い方を考えることが必要なのかもしれません。もしかすると、危険とちゃんと向き合うことは、たくましさを育む切っ掛けになるのかもしれません。

2016年07月29日
2016年07月28日
収穫・・・失敗! 7月16日
畑で大きく育った「金のたまご」。
そろそろいいかな、と思って2個収穫。
しかーーーーし!!
時期尚早
見た目での判断は禁物でした。
やはりメロンとは違いました。
蔓が枯れるのを待たなければいけませんでした。
赤いはずの中は、まだまだ白っぽくて・・・
匂いは甘くておいしそうにはなっていたのですが・・・


7月28日現在、まだ蔓は青々としています。
そろそろいいかな、と思って2個収穫。
しかーーーーし!!
時期尚早
見た目での判断は禁物でした。
やはりメロンとは違いました。
蔓が枯れるのを待たなければいけませんでした。
赤いはずの中は、まだまだ白っぽくて・・・
匂いは甘くておいしそうにはなっていたのですが・・・


7月28日現在、まだ蔓は青々としています。
2016年07月12日
水分補給について
必要な水分摂取量。大人と子どもで、目安の計算が違っているようです。
一日の目安として、それぞれの量に体重(kg)をかけます。
ただし、食事から取る水分も含んでいます。
乳児>150mℓ ※5kgの場合、150×5=450(mℓ)
幼児>100mℓ ※18kgの場合、100×18=1800(mℓ)=1.8ℓ
学童>80mℓ ※30kgの場合、80×30=2400(mℓ)=2.4ℓ
大人>50mℓ ※60kgの場合、50×60=3000(mℓ)=3ℓ
そして、飲み物ですが、清涼飲料水は糖分が多く、取り過ぎると血糖値の上がり下がりが激しくなるため、肥満ばかりか、「キレやすさ」にもつながるというデータがあります。水分補給目的ではリスクが大きいようです。スポーツドリンクもその中に含まれますが、電解質やアミノ酸、ミネラルなど有益なものも含まれているので、グレーゾーン。前に歯医者さんに聞いたところ、スポーツドリンクは糖分が多いにもかかわらず、水感覚で飲まれるため、虫歯の原因にもなっているとか。となれば、麦茶辺りが無難。体は冷やしてくれるし、血の流れも良くしてくれるとのこと。本当は冷たいより、温い方が体には優しいそうですが・・・この暑さ・・・難しいところです。
「水筒に入れてたら、ジュースでもいいの?」
児童館では、毎度おなじみの子どもの質問です。
児童館では、ジュース(先ほどの「清涼飲料水」)は嗜好品。お菓子と同じ扱いにしています。
したがって、おやつの時間だけのものとしています。
しかし、ジュースの方がおいしい。
どうせ飲むならおいしい方がいい。
老若男女、その思いが多数派だと思います。
無理からぬ質問です。
気持ちは重々わかりますが、児童館では区別をさせてもらっています。
児童館で水分補給となっているのは、目的のハッキリしている「お茶・水・スポーツドリンク」です。
※スポーツドリンクは、グレーゾーンではありますが。
また、多目のご準備をお勧めしました。ただ、足りないからだけではありません。
それは、水筒のお茶を切らした子が、友達に分けてもらっている場面を見かけるからです。自分のお茶を、友達に分けてあげるという行為自体は、ほほえましい光景です。しかし、分けてくれる子に無理がかからないとも限りません。他にないならまだしも、水道をひねれば、水は出てくるのですから。それに、分け方によっては、衛生面の不安も出てきます。多目のご準備をお勧めするのには、そんな背景もあります。
もちろん、水道水で補うのであれば、何ら問題はありません。
一日の目安として、それぞれの量に体重(kg)をかけます。
ただし、食事から取る水分も含んでいます。
乳児>150mℓ ※5kgの場合、150×5=450(mℓ)
幼児>100mℓ ※18kgの場合、100×18=1800(mℓ)=1.8ℓ
学童>80mℓ ※30kgの場合、80×30=2400(mℓ)=2.4ℓ
大人>50mℓ ※60kgの場合、50×60=3000(mℓ)=3ℓ
そして、飲み物ですが、清涼飲料水は糖分が多く、取り過ぎると血糖値の上がり下がりが激しくなるため、肥満ばかりか、「キレやすさ」にもつながるというデータがあります。水分補給目的ではリスクが大きいようです。スポーツドリンクもその中に含まれますが、電解質やアミノ酸、ミネラルなど有益なものも含まれているので、グレーゾーン。前に歯医者さんに聞いたところ、スポーツドリンクは糖分が多いにもかかわらず、水感覚で飲まれるため、虫歯の原因にもなっているとか。となれば、麦茶辺りが無難。体は冷やしてくれるし、血の流れも良くしてくれるとのこと。本当は冷たいより、温い方が体には優しいそうですが・・・この暑さ・・・難しいところです。
「水筒に入れてたら、ジュースでもいいの?」
児童館では、毎度おなじみの子どもの質問です。
児童館では、ジュース(先ほどの「清涼飲料水」)は嗜好品。お菓子と同じ扱いにしています。
したがって、おやつの時間だけのものとしています。
しかし、ジュースの方がおいしい。
どうせ飲むならおいしい方がいい。
老若男女、その思いが多数派だと思います。
無理からぬ質問です。
気持ちは重々わかりますが、児童館では区別をさせてもらっています。
児童館で水分補給となっているのは、目的のハッキリしている「お茶・水・スポーツドリンク」です。
※スポーツドリンクは、グレーゾーンではありますが。
また、多目のご準備をお勧めしました。ただ、足りないからだけではありません。
それは、水筒のお茶を切らした子が、友達に分けてもらっている場面を見かけるからです。自分のお茶を、友達に分けてあげるという行為自体は、ほほえましい光景です。しかし、分けてくれる子に無理がかからないとも限りません。他にないならまだしも、水道をひねれば、水は出てくるのですから。それに、分け方によっては、衛生面の不安も出てきます。多目のご準備をお勧めするのには、そんな背景もあります。
もちろん、水道水で補うのであれば、何ら問題はありません。
2016年07月07日
ドロバチの巣!?
昨日、「蜂の巣発見!」という職員の声。
見に行きますと、ちょうど出入り口の上にドロバチ(スズバチ?)の巣を発見。


直ちに殺虫剤を噴射!
一夜経って、翌日の今朝、除去作業。
これが又頑丈で、金槌で粉砕。
蜂の子が出てくるかと思いきや、おびただしい緑のクモ。


まさか!毒グモの巣?
調べてみると、どうやらハチが子どものために蓄えていたクモ(サツマノミダマシ?)らしいです。
巣は子ども部屋しかなく、成虫は餌を搬入するだけ。
住んではいないそうです。
ちなみに、毒グモでもなかったようです。
まずは一安心。
成虫が住んでるわけでもないし、おとなしいハチだし、
芋虫を狩ってくれるし、見逃しても大丈夫だという情報もありました。
しかし、好奇心旺盛な子ども達。
訪れるハチを怒らせないとも限りません。
それに、ハチはハチ。
怖がる人もいますしね。
こういった場所では、やはり巣の除去ってことになります。
ごめんね、今度は別の所に作ってね。
そして除去作業は、無事完了!

見に行きますと、ちょうど出入り口の上にドロバチ(スズバチ?)の巣を発見。


直ちに殺虫剤を噴射!
一夜経って、翌日の今朝、除去作業。
これが又頑丈で、金槌で粉砕。
蜂の子が出てくるかと思いきや、おびただしい緑のクモ。


まさか!毒グモの巣?
調べてみると、どうやらハチが子どものために蓄えていたクモ(サツマノミダマシ?)らしいです。
巣は子ども部屋しかなく、成虫は餌を搬入するだけ。
住んではいないそうです。
ちなみに、毒グモでもなかったようです。
まずは一安心。
成虫が住んでるわけでもないし、おとなしいハチだし、
芋虫を狩ってくれるし、見逃しても大丈夫だという情報もありました。
しかし、好奇心旺盛な子ども達。
訪れるハチを怒らせないとも限りません。
それに、ハチはハチ。
怖がる人もいますしね。
こういった場所では、やはり巣の除去ってことになります。
ごめんね、今度は別の所に作ってね。
そして除去作業は、無事完了!

2016年07月06日
畑近況
暑い日が続きます。
太陽の光も、「これでもかっ!」というくらいの勢いです。
あしたば農園の作物達は、暑さに負けずグングン育っています。
キュウリなどは、もう収穫が始まり、
時折、子ども達のおやつ(?)として、登場しています。
まずはサツマイモ。
右から、エレガントサマー、シルクスイート、安納芋です。
残念ながら、昨年に引き続き安納芋は不調です。

そうそう、もうじき花がつく頃です。
サツマイモはヒルガオ科。朝顔などに近い仲間です。色合いはなかなかの貴婦人です。
ご覧になりたいなら、気をつけておいてください。
そしてメロン。・・・と思いきやスイカ!
メロンと思って育てていましたが、
ちょっとした「みにくいアヒルの子(?)」。
実はスイカだったことが判明。
同僚の「線が入っているようですが、本当にメロン?」の一言が発端。
調べてみると、「西瓜」の文字が!!
収穫前に気付いたのは、不幸中(?)の幸い。
収穫のタイミングが、メロンとは違うみたいですから。
果たして、白鳥となってくれますか?!



お次はトウモロコシ。
こちらは防鳥対策を思案した結果、
今年は防鳥テープを試すことに。
効果は経過観察中。実がつき始めている、これからが正念場!


キュウリ。どんどん実ってる健康優良児。



トマトも負けてはいません。



そして、枝豆。
花も終わり、鈴なりにサヤがついています。
中の豆は、まだまだ発育途上。


遊びに来てる子が!

最後にルーキーとなります3種。
シソ、オクラ、ピーマン。



畑だけではありません。
花壇も賑やかです。
ヒマワリ。

玄関横でも。

ゴーヤ。




この子達の元気にあやかりながら、励まされながら、そして栄養をいただきながら、この猛暑をみんなで乗り切っていきたいと思います♪
太陽の光も、「これでもかっ!」というくらいの勢いです。
あしたば農園の作物達は、暑さに負けずグングン育っています。
キュウリなどは、もう収穫が始まり、
時折、子ども達のおやつ(?)として、登場しています。
まずはサツマイモ。
右から、エレガントサマー、シルクスイート、安納芋です。
残念ながら、昨年に引き続き安納芋は不調です。

そうそう、もうじき花がつく頃です。
サツマイモはヒルガオ科。朝顔などに近い仲間です。色合いはなかなかの貴婦人です。
ご覧になりたいなら、気をつけておいてください。
そしてメロン。・・・と思いきやスイカ!
メロンと思って育てていましたが、
ちょっとした「みにくいアヒルの子(?)」。
実はスイカだったことが判明。
同僚の「線が入っているようですが、本当にメロン?」の一言が発端。
調べてみると、「西瓜」の文字が!!
収穫前に気付いたのは、不幸中(?)の幸い。
収穫のタイミングが、メロンとは違うみたいですから。
果たして、白鳥となってくれますか?!



お次はトウモロコシ。
こちらは防鳥対策を思案した結果、
今年は防鳥テープを試すことに。
効果は経過観察中。実がつき始めている、これからが正念場!


キュウリ。どんどん実ってる健康優良児。



トマトも負けてはいません。



そして、枝豆。
花も終わり、鈴なりにサヤがついています。
中の豆は、まだまだ発育途上。


遊びに来てる子が!

最後にルーキーとなります3種。
シソ、オクラ、ピーマン。



畑だけではありません。
花壇も賑やかです。
ヒマワリ。

玄関横でも。

ゴーヤ。




この子達の元気にあやかりながら、励まされながら、そして栄養をいただきながら、この猛暑をみんなで乗り切っていきたいと思います♪
2016年07月05日
ささのは さ~ら、さら♪

7月7日は、七夕。
天の川を挟んで、織り姫と彦星が年1度会うことを許された日です。
晴れた夜空なら、その喜びにあやかれるのですが、
それはもう天気次第。
雲に遮られたなら、それもかないません。
時には水入らずで会っていただこうと、思いやりの気持ちで空を仰ぐしかありません。
私たちに見えないだけで、雲の向こうには満天の星が広がっているのですから。
「年に1度だなんて可哀想~」だなんて言っちゃう人もいますが、
私たちが100歳生きたとしても、36500日。
生まれてすぐ一緒だったなんてカップルは滅多にないでしょうから、
更にぐ~んと少なくなります。
ところで、織り姫とされている星「ベガ」は、3億8600万歳~5億7200万歳。
彦星の「アルタイル」は、10億歳未満。
一年間会わなかったとしても、相当な数です。
しかも、その一年が気持ちを新鮮にする時間だとしたら・・・。
う~ん、どっちが可哀想なのやら。
昔、そんな内容の笑い話を聞いたことがあります。
さて、七夕と言えば、「短冊にお願い事」ですね。
織り姫が織物の名人だったと言うことから、
女の子のたしなみの上達を願ったのが始まりだったという説があります。
今では老若男女を問わず願い事をしますね。
願い事の書き方ですが、「かなう書き方」「かなわない書き方」があるそうです。
【かなう書き方】
○「~になりますように」といった他人任せでなく、「~になる」と断言。
成功イメージを紙に書くことは、自分を動かす意味でも良いことのようです。
○「~になりました。ありがとうございました」
「~ができました。これからが楽しみです」
もうかなったことにして、その後に余裕の一言。
【かなわない書き方】
○悪いことを基準にした書き方。
「病気になりませんように」
→「元気いっぱいで、毎日がウルトラハッピーです」と言い切る。
「試験に落ちませんように」
→「試験に合格しました。ますますがんばるぞ!」とかなった時をイメージ。
謙虚さは美徳です。でも、年に1度は「ほら吹き」になってみるのも良い事かもしれません。
7月7日までは、児童館の「七夕」期間です。
お迎えの際などに、お家の方も「大胆に」願い事をされてみてはいかがですか?
2016年06月16日
子どもを見ていて
夏場の熱中症予防として、「補給用のお茶」の提案をさせていただきました。
昔話となってしまいますが、私(峰)が小学生だった頃を思い出してみると、遠足など特別な場合以外で水筒を持っていった記憶がありません。
ちなみに保育園がありませんでしたので、団体生活は小学校からです。
全て学校の水道水。周りもそうでしたから、別に違和感なくそうしていました。
来館する子ども達は、全員ではありませんが、水道水をためらう子を少なからず見かけます。やむを得ず、他の子から分けてもらっている子もいます。
確かに、この季節は水が温い。当館などは、水道管が露出しているので、水が熱せられ、お湯が出てしまうこともあります。バスタブがあれば、溜めて一風呂浴びたい感じです(笑)。それに、味を比較しても、お家で準備していただいたものの方が飲みやすいかもしれません。飲めれば良いと思って飲んでいた私からすれば、今の子はグルメが多い(笑)。おまけに水筒は保温性抜群!冷え冷えです。
水道水世代(?)としては、問題なければ、水筒などいらない気もしたりします。かつては水をお店で買うことに、もったいなささえ感じていました。とは言え、水分が補給しやすい状態にしてあげるのは大切なことです。できるだけおいしいものにしてあげた方が、進んで水分を補給するきっかけになるのかもしれませんしね。
毎日のように、誰かがどこかで喧嘩を始めます。トラブルはない方が良いのですが、喧嘩は個性のぶつかり合い、主張のぶつかり合いという面も持っています。自分の立場、譲歩と主張のバランス、トラブルの回避、そしてルールを学ぶ場でもあります。言葉や経験の少ない子ども達にとっては、喧嘩という表現に走ってしまいがちなのはわかるような気がします。男の子と女の子の喧嘩では、初め言い合いだったものが、女の子の口に勝てなくなってしまい、男の子が手を出してしまうパターン。勝手な要求なのに、受け入れてくれない相手を逆恨みするパターン。その他様々なパターンがあるようです。そして、どれも子ども特有とは言えないものばかり。一緒に解決すると、私(大人)にとっても勉強になることがいっぱいです。喧嘩はいけないことだと教えられては来ましたが、学ぶべき事もたくさん含んでいるように感じます。大人が喧嘩に参加しては別物になってしまいますが、時には一緒に解決していくというのもいいかもしれません。またその中で、ルールを教え、「上手な喧嘩」を共に考えることは大切なことだと感じます。
何せ、大人が勉強になります。
昔話となってしまいますが、私(峰)が小学生だった頃を思い出してみると、遠足など特別な場合以外で水筒を持っていった記憶がありません。
ちなみに保育園がありませんでしたので、団体生活は小学校からです。
全て学校の水道水。周りもそうでしたから、別に違和感なくそうしていました。
来館する子ども達は、全員ではありませんが、水道水をためらう子を少なからず見かけます。やむを得ず、他の子から分けてもらっている子もいます。
確かに、この季節は水が温い。当館などは、水道管が露出しているので、水が熱せられ、お湯が出てしまうこともあります。バスタブがあれば、溜めて一風呂浴びたい感じです(笑)。それに、味を比較しても、お家で準備していただいたものの方が飲みやすいかもしれません。飲めれば良いと思って飲んでいた私からすれば、今の子はグルメが多い(笑)。おまけに水筒は保温性抜群!冷え冷えです。
水道水世代(?)としては、問題なければ、水筒などいらない気もしたりします。かつては水をお店で買うことに、もったいなささえ感じていました。とは言え、水分が補給しやすい状態にしてあげるのは大切なことです。できるだけおいしいものにしてあげた方が、進んで水分を補給するきっかけになるのかもしれませんしね。
毎日のように、誰かがどこかで喧嘩を始めます。トラブルはない方が良いのですが、喧嘩は個性のぶつかり合い、主張のぶつかり合いという面も持っています。自分の立場、譲歩と主張のバランス、トラブルの回避、そしてルールを学ぶ場でもあります。言葉や経験の少ない子ども達にとっては、喧嘩という表現に走ってしまいがちなのはわかるような気がします。男の子と女の子の喧嘩では、初め言い合いだったものが、女の子の口に勝てなくなってしまい、男の子が手を出してしまうパターン。勝手な要求なのに、受け入れてくれない相手を逆恨みするパターン。その他様々なパターンがあるようです。そして、どれも子ども特有とは言えないものばかり。一緒に解決すると、私(大人)にとっても勉強になることがいっぱいです。喧嘩はいけないことだと教えられては来ましたが、学ぶべき事もたくさん含んでいるように感じます。大人が喧嘩に参加しては別物になってしまいますが、時には一緒に解決していくというのもいいかもしれません。またその中で、ルールを教え、「上手な喧嘩」を共に考えることは大切なことだと感じます。
何せ、大人が勉強になります。
2016年06月09日
不気味な物体
児童館の植え込みに不気味な物体がありました。
一体何?
ネットで調べてみましたが、
正体を確認できるものを見つけることはできませんでした。

ヒントとして見つかったのは、「虫こぶ」。
その画像を見ましたが、やはり同じものは見つけられませんでした。
中に何が詰まっているのか?
開けてみる勇気は、まだありません。
※本日(平成28年6月14日) 新たに・・・

一体何?
ネットで調べてみましたが、
正体を確認できるものを見つけることはできませんでした。

ヒントとして見つかったのは、「虫こぶ」。
その画像を見ましたが、やはり同じものは見つけられませんでした。
中に何が詰まっているのか?
開けてみる勇気は、まだありません。
※本日(平成28年6月14日) 新たに・・・

2016年01月26日
一難去って、また一難
昨日は大雪。
雪も溶け、難は去ったかと思いきや、
この寒波の影響で今度は断水。
児童館も出ていません。
保育園も断水の為、
登園を控えるよう言われているようです。
今日は児童館は通常開館。
とりあえずは、生活水。
とりわけ、トイレの水の確保。
児童館で用意したものは、バケツの雪。
・・・でも溶け方がとてもスローリー
間に合うのか!?

間もなく到着したのは、社協事務局から。

そして、役場(住民福祉課)から届けられた非常用の水。

みなさんのおかげで、差し当たってはしのげそうです。
ありがとうございました。
しかし、明日の開館が危ぶまれる事態。
一難去って、また一難。
余波は続いています。
雪も溶け、難は去ったかと思いきや、
この寒波の影響で今度は断水。
児童館も出ていません。
保育園も断水の為、
登園を控えるよう言われているようです。
今日は児童館は通常開館。
とりあえずは、生活水。
とりわけ、トイレの水の確保。
児童館で用意したものは、バケツの雪。
・・・でも溶け方がとてもスローリー
間に合うのか!?

間もなく到着したのは、社協事務局から。

そして、役場(住民福祉課)から届けられた非常用の水。

みなさんのおかげで、差し当たってはしのげそうです。
ありがとうございました。
しかし、明日の開館が危ぶまれる事態。
一難去って、また一難。
余波は続いています。
2016年01月25日
雪や困々(こんこん)
雪や こんこ♪
あられや こんこ♪
などと、悠長に歌ってられなかった今回の大雪。
申年は大荒れ。
そう言った人もいましたが、
いきなりの異常気象。
雪に不慣れな地域では、「立ち往生」続出です。
県下の学校も軒並み臨時休校。
ここ玄海町もご多分に漏れていません。
子どもたちは見慣れない雪景色に、
ハイテンションになっている事でしょう。
おまけに学校はお休みときてるんですから。
本日は学校に準じ、児童館もお休み。
静まりかえった施設の外は断続的な雪。
寂しさを際立たせます。
溶け始めているような気はしますが、
今度は明日の朝の凍結の心配が残ります。
雪だるまをこさえてみたのですが、
こんなに白く作れるのは珍しい。
それにしても、不慣れとは言え、不格好な雪だるまです。
20km走行で、やっとたどり着いた児童館。
辺り一面、風花の乱舞。
車を降りると、そこは雪国だった・・・みたいな・・・

施設の裏も、こんな感じ。

おきまりですが、雪だるま。

再び。真っ白。

玄関前。測ってみると・・・

【追記】
午後5時25分現在。館内気温4.6℃。多分館外、1℃くらい。
だいぶん溶けたようですが、未だちらつく雪。


あられや こんこ♪
などと、悠長に歌ってられなかった今回の大雪。
申年は大荒れ。
そう言った人もいましたが、
いきなりの異常気象。
雪に不慣れな地域では、「立ち往生」続出です。
県下の学校も軒並み臨時休校。
ここ玄海町もご多分に漏れていません。
子どもたちは見慣れない雪景色に、
ハイテンションになっている事でしょう。
おまけに学校はお休みときてるんですから。
本日は学校に準じ、児童館もお休み。
静まりかえった施設の外は断続的な雪。
寂しさを際立たせます。
溶け始めているような気はしますが、
今度は明日の朝の凍結の心配が残ります。
雪だるまをこさえてみたのですが、
こんなに白く作れるのは珍しい。
それにしても、不慣れとは言え、不格好な雪だるまです。
20km走行で、やっとたどり着いた児童館。
辺り一面、風花の乱舞。
車を降りると、そこは雪国だった・・・みたいな・・・

施設の裏も、こんな感じ。

おきまりですが、雪だるま。

再び。真っ白。

玄関前。測ってみると・・・

【追記】
午後5時25分現在。館内気温4.6℃。多分館外、1℃くらい。
だいぶん溶けたようですが、未だちらつく雪。


2016年01月25日
1月16日の安全教室に寄せて
平成7年1月17日午前5時46分。
忘れてはならない日です。
そう、阪神淡路大震災です。
自分に被害が及ばないと、
つい同じ名前のものは更新してしまいます。
大震災と言えば、「東日本大震災」の人も多いんじゃないでしょうか?
ニュースなどで耳に入り、「関東大震災」も「阪神淡路大震災」も、
「そう言えばあったもの」となってしまってる人もいるかもしれません。
でも一つとして同じ災害はありません。
ひとくくりに出来ない人々の悲しみや苦しみがそこにあります。
決して「上書き保存」にはできません。
それに私たちが暮らしているのは、地震列島・日本です。
「明日は我が身」を忘れてはいけません。
児童館のある玄海町は、地震の珍しい地域です。
だからこそ、ピンとこない災害の一つが地震。
これが東海地方となれば事情が違ってくるのでしょう。
ずいぶん前ですが、三重県の方に旅行した事がありました。
その時に驚いたのが、バスの掲示。
地震の際の対応が書かれているのです。
その時、地震に対する意識の高さに驚いた事を覚えています。
忘れてはならない日です。
そう、阪神淡路大震災です。
自分に被害が及ばないと、
つい同じ名前のものは更新してしまいます。
大震災と言えば、「東日本大震災」の人も多いんじゃないでしょうか?
ニュースなどで耳に入り、「関東大震災」も「阪神淡路大震災」も、
「そう言えばあったもの」となってしまってる人もいるかもしれません。
でも一つとして同じ災害はありません。
ひとくくりに出来ない人々の悲しみや苦しみがそこにあります。
決して「上書き保存」にはできません。
それに私たちが暮らしているのは、地震列島・日本です。
「明日は我が身」を忘れてはいけません。
児童館のある玄海町は、地震の珍しい地域です。
だからこそ、ピンとこない災害の一つが地震。
これが東海地方となれば事情が違ってくるのでしょう。
ずいぶん前ですが、三重県の方に旅行した事がありました。
その時に驚いたのが、バスの掲示。
地震の際の対応が書かれているのです。
その時、地震に対する意識の高さに驚いた事を覚えています。
2015年09月24日
新たな危険
出勤前、朝のワイドショーを観ていましたら、
気になる話題が取り上げられていました。
主人公は、「ツマアカスズメバチ」。
相当な繁殖力のようです。
1つの巣に5千から1万。
近づかなければ大丈夫!・・・と言うわけにもいかず、
狙って人を襲いに来ることもあるそうです。
こわ~っ!
中国南部から東南アジアに生息するハチで、
韓国では既に生態系への影響が出ているらしく、
日本でも近年、対馬で確認されたそうです。
国は多額の予算をつけ対策をしたそうですが・・・。
先日とうとう北九州で見つかったらしく、
その繁殖状況が危ぶまれています。
北九州と言えば、そう遠くはありませんね。
刺されると、もちろん腫れますし、
アナフィラキシーショックによる絶命もあるそうです。
アナフィラキシーショックは「2回目が・・」と言われますが、
スズメバチは何度も刺す習性があるらしく、
1度の遭遇で、2回目もあるそうですので、要警戒!
貿易船でやってきたという説が有力で、
当座は大きな貿易港周辺が危ないそうですが・・・。
直接の危険もありますが、
ミツバチが大好物なため、
養蜂業、また野菜の受粉にミツバチを使う農業に被害をもたらし、
食物の値上げなど、生活への影響も考えられるそうです。
とかく、外来種というものは旺盛な繁殖力を持っていますからね。
他の生き物が対応しきれない間に増えちゃうようです。
自然豊かなこの町。
様々な虫たちに紛れられたら、まさにホラーです。
体長は2~3cm。尾っぽの部分が赤い。
同じ外来種で、話題にもなったセアカゴケグモ。
赤って色は、「危険」を好む色なのでしょうか。
赤というより、オレンジ色っぽい・・・

かなり高いところにも巣を作るそうです。しかも、デカイッ!

見かけたら、ご注意を!
気になる話題が取り上げられていました。
主人公は、「ツマアカスズメバチ」。
相当な繁殖力のようです。
1つの巣に5千から1万。
近づかなければ大丈夫!・・・と言うわけにもいかず、
狙って人を襲いに来ることもあるそうです。
こわ~っ!
中国南部から東南アジアに生息するハチで、
韓国では既に生態系への影響が出ているらしく、
日本でも近年、対馬で確認されたそうです。
国は多額の予算をつけ対策をしたそうですが・・・。
先日とうとう北九州で見つかったらしく、
その繁殖状況が危ぶまれています。
北九州と言えば、そう遠くはありませんね。
刺されると、もちろん腫れますし、
アナフィラキシーショックによる絶命もあるそうです。
アナフィラキシーショックは「2回目が・・」と言われますが、
スズメバチは何度も刺す習性があるらしく、
1度の遭遇で、2回目もあるそうですので、要警戒!
貿易船でやってきたという説が有力で、
当座は大きな貿易港周辺が危ないそうですが・・・。
直接の危険もありますが、
ミツバチが大好物なため、
養蜂業、また野菜の受粉にミツバチを使う農業に被害をもたらし、
食物の値上げなど、生活への影響も考えられるそうです。
とかく、外来種というものは旺盛な繁殖力を持っていますからね。
他の生き物が対応しきれない間に増えちゃうようです。
自然豊かなこの町。
様々な虫たちに紛れられたら、まさにホラーです。
体長は2~3cm。尾っぽの部分が赤い。
同じ外来種で、話題にもなったセアカゴケグモ。
赤って色は、「危険」を好む色なのでしょうか。
赤というより、オレンジ色っぽい・・・

かなり高いところにも巣を作るそうです。しかも、デカイッ!

見かけたら、ご注意を!
2015年05月28日
自転車も「車」
朝のニュースで知ったこと。
改正された道路交通法が、今年の6月(来週月曜日)から施行されるそうですね。
いろいろとあるのでしょうが、
ニュースで取り上げられていたのは「自転車」。
内容は「新設」ではなく、これまでの「強化」のようです。
これまで以上に「切符」を切られることが多くなるかもしれません。
「切符」ばかりでなく、懲役や反則金(最高100万円)も・・・。
軽車両というのは知っていたのですが、
実感としては、歩くのと同じ扱いでした。
改めて、自転車は「車」なんだと感じさせられる今回の改正。
ネットから拾った情報によると、
強化されるのは次の14項目。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
並んで運転したり、2人乗り、傘差し、携帯電話、イヤホン、スピード違反、危険運転なども、上の項目のどこかに含まれています。もちろん、乗れるのは車道が原則。一旦停止、一方通行での逆走なんかも・・・。
自転車の事故が増加したという背景があるということなので、仕方のないことですが、自転車に乗るのもちょっと緊張してしまいます。もっとも、私個人はここ数十年、自転車とは縁がないのですが・・・。
3年以内に2回摘発されたら、3時間の「安全教室」を受講しなくてはいけないそうです。受講料は5,700円。受講しなければ、これまた罰金が科せられます。
適用は14歳以上だそうです(なんと中学生から!)。
これを機に自転車の乗り方を話し合われてはいかがでしょうか?
中学生で急に身につくものではありません。
14歳前にしっかり身につけさせたいものです。
その際はもちろん、
罰せられるからでなく、「危険だから守る」ということも忘れずに。
>みどり児童館 峰
改正された道路交通法が、今年の6月(来週月曜日)から施行されるそうですね。
いろいろとあるのでしょうが、
ニュースで取り上げられていたのは「自転車」。
内容は「新設」ではなく、これまでの「強化」のようです。
これまで以上に「切符」を切られることが多くなるかもしれません。
「切符」ばかりでなく、懲役や反則金(最高100万円)も・・・。
軽車両というのは知っていたのですが、
実感としては、歩くのと同じ扱いでした。
改めて、自転車は「車」なんだと感じさせられる今回の改正。
ネットから拾った情報によると、
強化されるのは次の14項目。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
並んで運転したり、2人乗り、傘差し、携帯電話、イヤホン、スピード違反、危険運転なども、上の項目のどこかに含まれています。もちろん、乗れるのは車道が原則。一旦停止、一方通行での逆走なんかも・・・。
自転車の事故が増加したという背景があるということなので、仕方のないことですが、自転車に乗るのもちょっと緊張してしまいます。もっとも、私個人はここ数十年、自転車とは縁がないのですが・・・。
3年以内に2回摘発されたら、3時間の「安全教室」を受講しなくてはいけないそうです。受講料は5,700円。受講しなければ、これまた罰金が科せられます。
適用は14歳以上だそうです(なんと中学生から!)。
これを機に自転車の乗り方を話し合われてはいかがでしょうか?
中学生で急に身につくものではありません。
14歳前にしっかり身につけさせたいものです。
その際はもちろん、
罰せられるからでなく、「危険だから守る」ということも忘れずに。
>みどり児童館 峰
2015年02月10日
地域の支援
1月10日。
行事活動は「缶蹴り」でした。
その終わり近くに、
前館長が稲わらを持って来てくださいました。
お住まいの地域の子ども達と餅米の栽培。(餅つきもされました)
大量に出た稲わら。
児童館が作物を栽培していることは、もちろんご承知。
使ってくれ、ということで持ってきてくださいました。
私と2人で、しばし子ども達の缶蹴りを観戦。
そこに現在前館長の同僚となっている方が、
トラクターに乗って通りかかられました。
畑仕事の帰りだったようです。
前館長はその方に近より話をされ、
児童館の畑を耕していただけることになりました。
人力ではどれ程かかるかわからない作業を、
あっという間に終わらせてくださいました。
地域の方々の支援の有り難さを改めて感じました。
さて、問題はその活用。
何を栽培するか、早急に決めなければなりません。
折角整えられた畑。
暖かくなってきたら、また雑草園です。

行事活動は「缶蹴り」でした。
その終わり近くに、
前館長が稲わらを持って来てくださいました。
お住まいの地域の子ども達と餅米の栽培。(餅つきもされました)
大量に出た稲わら。
児童館が作物を栽培していることは、もちろんご承知。
使ってくれ、ということで持ってきてくださいました。
私と2人で、しばし子ども達の缶蹴りを観戦。
そこに現在前館長の同僚となっている方が、
トラクターに乗って通りかかられました。
畑仕事の帰りだったようです。
前館長はその方に近より話をされ、
児童館の畑を耕していただけることになりました。
人力ではどれ程かかるかわからない作業を、
あっという間に終わらせてくださいました。
地域の方々の支援の有り難さを改めて感じました。
さて、問題はその活用。
何を栽培するか、早急に決めなければなりません。
折角整えられた畑。
暖かくなってきたら、また雑草園です。

2014年08月28日
一期一会
「一期一会」。
この言葉は確か「禅」の言葉だと記憶しています。
深い意味は分かりませんが、
「今を大切に」という意味合いだったと思います。
私のような愚人は、時にしたり顔で使い、
立派な人間に見せようとします。
しかしよく考えてみると、言い方を変えれば、
「過去や未来にとらわれずに、今を一番に考える」ということかも知れません。
そうしてみると、日頃関わっている、特に低学年の子は、
正に「一期一会」で生きているようにも見えます。
「今を大切に」という大人。
「先のことを考えて行動しなさい」と言う大人。
「自分のこれまでの行動を省みなさい」と言う大人。
「周囲を意識しなさい」という大人。
子とも達には、どう映っているのでしょう。
後先を考えて行動すること。
反省の上に行動すること。
確かに生活する上で大切な事です。
でもそのために、我慢や無視をせざるをえないことが
少なからずあるように思います。
「今を生きる」という上では、
子ども達の方が長けているように思えます。
もちろん、それを許してくれる環境あってのことですが。
お年寄りにも「一期一会」で生きている方がいらっしゃいます。
後先や反省を意識することから解放された方々です。
生活の中では、「一期一会」にかまけてられないという現実もあります。
目をつぶることで、調和も取っています。
ともすると、そう言った視点でばかり考えて、
「一期一会」の心を、知らず知らず消そうとしているかも知れません。
時には「悪」だと決めつけてしまう危険もあります。
先に進もうとすると、
「一期一会」が難しい宿題を出してきます。
しかし、心を躍動させ、生きている印を刻んでくれるのも、
また「一期一会」。
子どもやお年寄りに、
よからぬ感情を抱いてしまうとき、
案外「一期一会」を持っていられることへの嫉妬があるのかも知れませんね。
心が躍動できることは、何より気持ちのよいことですから。
(多分これは失った者の方がより実感できること)
「一期一会」は、「幸せ」の大切な要素かも知れません。
そう考えると大切にしなければなりません。
どうやって生活と折り合いを付けて、
「一期一会」を守っていくか。
子ども達がこれから幸せを育んでいくためには、
またそれを支援していく上では大事なもののように感じます。
他人事ではなく、私にとっても。
この言葉は確か「禅」の言葉だと記憶しています。
深い意味は分かりませんが、
「今を大切に」という意味合いだったと思います。
私のような愚人は、時にしたり顔で使い、
立派な人間に見せようとします。
しかしよく考えてみると、言い方を変えれば、
「過去や未来にとらわれずに、今を一番に考える」ということかも知れません。
そうしてみると、日頃関わっている、特に低学年の子は、
正に「一期一会」で生きているようにも見えます。
「今を大切に」という大人。
「先のことを考えて行動しなさい」と言う大人。
「自分のこれまでの行動を省みなさい」と言う大人。
「周囲を意識しなさい」という大人。
子とも達には、どう映っているのでしょう。
後先を考えて行動すること。
反省の上に行動すること。
確かに生活する上で大切な事です。
でもそのために、我慢や無視をせざるをえないことが
少なからずあるように思います。
「今を生きる」という上では、
子ども達の方が長けているように思えます。
もちろん、それを許してくれる環境あってのことですが。
お年寄りにも「一期一会」で生きている方がいらっしゃいます。
後先や反省を意識することから解放された方々です。
生活の中では、「一期一会」にかまけてられないという現実もあります。
目をつぶることで、調和も取っています。
ともすると、そう言った視点でばかり考えて、
「一期一会」の心を、知らず知らず消そうとしているかも知れません。
時には「悪」だと決めつけてしまう危険もあります。
先に進もうとすると、
「一期一会」が難しい宿題を出してきます。
しかし、心を躍動させ、生きている印を刻んでくれるのも、
また「一期一会」。
子どもやお年寄りに、
よからぬ感情を抱いてしまうとき、
案外「一期一会」を持っていられることへの嫉妬があるのかも知れませんね。
心が躍動できることは、何より気持ちのよいことですから。
(多分これは失った者の方がより実感できること)
「一期一会」は、「幸せ」の大切な要素かも知れません。
そう考えると大切にしなければなりません。
どうやって生活と折り合いを付けて、
「一期一会」を守っていくか。
子ども達がこれから幸せを育んでいくためには、
またそれを支援していく上では大事なもののように感じます。
他人事ではなく、私にとっても。
2014年07月05日
みどり農園
児童館では、低学年(1、2年生)、中学年(3、4年生)、高学年(5、6年生)の3つのブロックに分かれて、
ブロック活動をしています。
その一環として、児童館の畑にそれぞれ作物を育てています。
低学年はサツマイモ(安納芋、ひめあやか、パープルスイートロード)3種。
中学年はトウモロコシ3種。
高学年はソラマメ(駒栄)、枝豆(湯上がり娘、快豆黒頭巾)、合わせて3種。
その他畑で出来ているのは、ジャガイモ、トマト、ミニトマト、そうめんカボチャ、ミニカボチャ、スイカ、キュウリ、ピーマンなど。
【みどり農園】

【枝豆の花(湯上がり娘)】

【枝豆の花(快豆黒頭巾)】

【ソラマメの花(駒栄)】

【ジャガイモの花】

【トマトの花】

【キュウリの花】

【そうめんカボチャの花】

【スイカの花】

【スイカの実】

【トウモロコシの花】

大雨(児童館が出来て毎年一度は川が氾濫します)、大風、日照りに気温など・・・。
私達のお世話以上に自然に左右される作物作り。
どうぞ、大きな被害にあわず、たくさんの実りとなりますように。
追記>>>じぇじぇじぇっ(`jjj')/ 今度の水曜日、台風接近!
※表現がちょっと古くなってしまった事をお詫び申し上げます(笑)・・・笑い事じゃないですが・・・
ブロック活動をしています。
その一環として、児童館の畑にそれぞれ作物を育てています。
低学年はサツマイモ(安納芋、ひめあやか、パープルスイートロード)3種。
中学年はトウモロコシ3種。
高学年はソラマメ(駒栄)、枝豆(湯上がり娘、快豆黒頭巾)、合わせて3種。
その他畑で出来ているのは、ジャガイモ、トマト、ミニトマト、そうめんカボチャ、ミニカボチャ、スイカ、キュウリ、ピーマンなど。
【みどり農園】

【枝豆の花(湯上がり娘)】

【枝豆の花(快豆黒頭巾)】

【ソラマメの花(駒栄)】

【ジャガイモの花】

【トマトの花】

【キュウリの花】

【そうめんカボチャの花】

【スイカの花】

【スイカの実】

【トウモロコシの花】

大雨(児童館が出来て毎年一度は川が氾濫します)、大風、日照りに気温など・・・。
私達のお世話以上に自然に左右される作物作り。
どうぞ、大きな被害にあわず、たくさんの実りとなりますように。
追記>>>じぇじぇじぇっ(`jjj')/ 今度の水曜日、台風接近!
※表現がちょっと古くなってしまった事をお詫び申し上げます(笑)・・・笑い事じゃないですが・・・
2014年05月24日
保護者懇談会後記
長くなり恐縮ですが、保護者懇談会に関して少々・・・
協議の中では、来年度の小中一貫校開校後の児童館の動向に関する話題が中心となりました。
これまでの懇談会でも触れました「児童館と放課後児童クラブの違い」も話題に上りました。
実際玄海町に児童館が設立された当時、職員自体にもその区別がよくついておらず、
地域のニーズにお応えする形で運営を行い、その一方で「児童館とは?」ということについて職員なりに学び、考えて参りました。
その中で、「玄海町の児童館」と「そもそもの児童館」の違いが見えてきました。
しかし、体験を重ねる中で理解してきたものを、言葉で説明するのは大変難しいものです。
おまけに「そもそもの児童館」でなく、ご家庭のニーズを元に運営を進めて参りましたので、「そもそもの児童館」とは異なってしまっている部分もあります。そんな中で、「児童館と放課後児童クラブの違い」をご説明しても混乱を生んでしまうのではないかと思います。ご利用のご家庭には、今の児童館が「児童館」。違うんだったら、今までの児童館は一体?となられても仕方ないことです。
児童館として発足はしましたが、ご家庭のニーズにお応えしていく中で、放課後児童クラブの要素が濃くなっているようです。利用されるご家庭の要望も当然その傾向が強く出ています。お断りしておきますが、それはこれまでの運営の中では当然の流れだと思っています。
児童館と放課後児童クラブには、それぞれの役割があります。
(たくさんの先輩方もご覧になれる場で大変不遜ではありますが・・・間違っていたらどうぞご教示下さい)
児童館は、子ども達の健やかな成長を後押しする地域のコミュニティの場、
放課後児童クラブは、親御さんに変わって子ども達の健やかな成長を見守る場。
といったところでしょうか。
目的は似ているのですが、
子ども達への関わりは違う立場から行われます。
施設の構造、職員の配置でも異なることを前置きとして、
児童館は活動を中心として、子ども達にその指導やケアを行います。
子どもの集団の中で様々な成長を支援します。
放課後児童クラブは、留守家庭の代替の役割として、
ご家庭のニーズ、個別の関わりを重視します。
家庭に代わる見守りの中で健やかな成長を保護します。
従って、児童館では活動に必要な広さ、設備、職員などが考慮されています。
一方放課後児童クラブでは、子ども一人一人に必要な居場所(広さ)、
生活に困らない設備、関われる範囲を考慮した定員と職員などが必要になってきます。
様々な体験をさせたい。
そういったニーズには、児童館がお応えできると思います。
前述しましたように、地域のコミュニティの場でもありますので、
子育てに携わる家庭や地域の交流にもご利用頂けます。
また児童と言っても、0歳児から18歳までが児童館での「児童」ですので、
多様な子ども達との触れ合いの機会もご提供できると思います。
※因みに玄海町の児童館は、3歳以上と小学生が主な対象となっています。
仕事で家庭が留守になり、心配なので代わりに見てて欲しい。
できるだけ家庭の事情に考慮して欲しい。
そういったニーズには放課後児童クラブがお応えできると思います。
また放課後児童クラブは限られた子ども達しか利用できない為、
出入りが比較的自由な児童館より安全だと言えるかも知れません。
現在の児童館では、児童館運営の範囲内で可能な見守りをしています。
しかし、放課後児童クラブほど、
ご家庭や子ども達の事情に対応した見守りはできません。
そして、特に見守りが必要な低学年の利用が多いため、
その対応で活動の支援や体験の提供が限られてしまっているのが現状です。
どっちつかずと言えば、そう思われても仕方ないかも知れません。
とは言え、ご家庭のニーズで育てて頂いた児童館。
今の形がしっくりしているのかも知れません。
ご家庭へのより良い支援。
それはとても必要な事です。
少子化対策の面からも大いに意味のある事だと思います。
一方子供たちにとってのより良い環境作り。
それも大切な課題です。
私達は今後の地域の子育てを考える上で、
大きな局面に居合わせているのかも知れません。
今回の保護者懇談会では、行政の方から、
「本年度に方向性を示したい」とのお考えをお聞かせ頂きました。
このままの児童館運営で行くか、
もっと役割を明確に差別化して発展的な運営を目指すか、
現場は考えあぐねているところです。
けれど利用者あっての児童館。
私たちの意向よりも、
利用されている方々のお考えや目的が反映されなければなりません。
今はインターネットで
いろんな情報を得る事ができます。
機会があれば、
児童館の事、放課後児童クラブの事、
そして他の地域での取り組みなどをのぞいてみてください。
玄海町の児童館では、
「共に育て、共に育つ」を目的とした「共育」を理念としています。
児童館は、
いわばご家庭や地域の皆さんに子育てを共有して頂く場所です。
皆さんと情報や考えを持ち寄り、
子供たちの将来に続く、最善の形が見つかれば幸いです。
協議の中では、来年度の小中一貫校開校後の児童館の動向に関する話題が中心となりました。
これまでの懇談会でも触れました「児童館と放課後児童クラブの違い」も話題に上りました。
実際玄海町に児童館が設立された当時、職員自体にもその区別がよくついておらず、
地域のニーズにお応えする形で運営を行い、その一方で「児童館とは?」ということについて職員なりに学び、考えて参りました。
その中で、「玄海町の児童館」と「そもそもの児童館」の違いが見えてきました。
しかし、体験を重ねる中で理解してきたものを、言葉で説明するのは大変難しいものです。
おまけに「そもそもの児童館」でなく、ご家庭のニーズを元に運営を進めて参りましたので、「そもそもの児童館」とは異なってしまっている部分もあります。そんな中で、「児童館と放課後児童クラブの違い」をご説明しても混乱を生んでしまうのではないかと思います。ご利用のご家庭には、今の児童館が「児童館」。違うんだったら、今までの児童館は一体?となられても仕方ないことです。
児童館として発足はしましたが、ご家庭のニーズにお応えしていく中で、放課後児童クラブの要素が濃くなっているようです。利用されるご家庭の要望も当然その傾向が強く出ています。お断りしておきますが、それはこれまでの運営の中では当然の流れだと思っています。
児童館と放課後児童クラブには、それぞれの役割があります。
(たくさんの先輩方もご覧になれる場で大変不遜ではありますが・・・間違っていたらどうぞご教示下さい)
児童館は、子ども達の健やかな成長を後押しする地域のコミュニティの場、
放課後児童クラブは、親御さんに変わって子ども達の健やかな成長を見守る場。
といったところでしょうか。
目的は似ているのですが、
子ども達への関わりは違う立場から行われます。
施設の構造、職員の配置でも異なることを前置きとして、
児童館は活動を中心として、子ども達にその指導やケアを行います。
子どもの集団の中で様々な成長を支援します。
放課後児童クラブは、留守家庭の代替の役割として、
ご家庭のニーズ、個別の関わりを重視します。
家庭に代わる見守りの中で健やかな成長を保護します。
従って、児童館では活動に必要な広さ、設備、職員などが考慮されています。
一方放課後児童クラブでは、子ども一人一人に必要な居場所(広さ)、
生活に困らない設備、関われる範囲を考慮した定員と職員などが必要になってきます。
様々な体験をさせたい。
そういったニーズには、児童館がお応えできると思います。
前述しましたように、地域のコミュニティの場でもありますので、
子育てに携わる家庭や地域の交流にもご利用頂けます。
また児童と言っても、0歳児から18歳までが児童館での「児童」ですので、
多様な子ども達との触れ合いの機会もご提供できると思います。
※因みに玄海町の児童館は、3歳以上と小学生が主な対象となっています。
仕事で家庭が留守になり、心配なので代わりに見てて欲しい。
できるだけ家庭の事情に考慮して欲しい。
そういったニーズには放課後児童クラブがお応えできると思います。
また放課後児童クラブは限られた子ども達しか利用できない為、
出入りが比較的自由な児童館より安全だと言えるかも知れません。
現在の児童館では、児童館運営の範囲内で可能な見守りをしています。
しかし、放課後児童クラブほど、
ご家庭や子ども達の事情に対応した見守りはできません。
そして、特に見守りが必要な低学年の利用が多いため、
その対応で活動の支援や体験の提供が限られてしまっているのが現状です。
どっちつかずと言えば、そう思われても仕方ないかも知れません。
とは言え、ご家庭のニーズで育てて頂いた児童館。
今の形がしっくりしているのかも知れません。
ご家庭へのより良い支援。
それはとても必要な事です。
少子化対策の面からも大いに意味のある事だと思います。
一方子供たちにとってのより良い環境作り。
それも大切な課題です。
私達は今後の地域の子育てを考える上で、
大きな局面に居合わせているのかも知れません。
今回の保護者懇談会では、行政の方から、
「本年度に方向性を示したい」とのお考えをお聞かせ頂きました。
このままの児童館運営で行くか、
もっと役割を明確に差別化して発展的な運営を目指すか、
現場は考えあぐねているところです。
けれど利用者あっての児童館。
私たちの意向よりも、
利用されている方々のお考えや目的が反映されなければなりません。
今はインターネットで
いろんな情報を得る事ができます。
機会があれば、
児童館の事、放課後児童クラブの事、
そして他の地域での取り組みなどをのぞいてみてください。
玄海町の児童館では、
「共に育て、共に育つ」を目的とした「共育」を理念としています。
児童館は、
いわばご家庭や地域の皆さんに子育てを共有して頂く場所です。
皆さんと情報や考えを持ち寄り、
子供たちの将来に続く、最善の形が見つかれば幸いです。
2014年03月07日
セキュリティソフト
パソコンをお使いの方はご存じでしょうが、
必要なソフトの一つが「セキュリティソフト」。
インターネット上には、様々な危険があります。
情報を盗むためのもの、お金を奪い取るもの、
パソコンを壊してしまうもの・・・等々。
それを人の病気になぞらえて「ウィルス」といってますが、
その予防が「セキュリティソフト」。
残念ながら、これは予防。
風邪薬のように対処する薬ではありません。
感染しちゃったら、
最悪修復不可能です。
まあ、パソコンの場合は「総入れ替え」って手もありますが・・・。
インターネットといったら、特別なもののように思われがちですが、
よく考えてみると、背景が違うだけで普段の生活と同じです。
泥棒はいるし、ズルする人はいるし、乱暴な人はいるし・・・。
ネットも日常の生活も大差は無いように思います。
大きな違いといえば、その範囲くらいでしょうか。
さて子ども達は、いろんな体験(情報)を糧として成長していきます。
しかし、自制心や社会性、常識が身についてないという意味では、
「セキュリティソフト」の入っていないパソコンと同じです。
つまり「やられ放題」、「されるがまま」です。
「セキュリティソフト」を身につけてもらうしかありません。
プログラムのインストールが終わるまでは、
大人の「セキュリティソフト」で対応するしかありません。
しかし、大人も万全なものを持っているとは限りません。
油断や慢心からウィルスは侵入してきます。
いわゆる「セキュリティホール」です。
油断大敵です。
大人も常にプログラムを更新していかなければなりません。
「子供の意志を尊重」といっても、
自分を築いている最中。
子供に全く委ねてしまうのは危険です。
それこそ、「ウィルスの仕業」に踊らされているだけかもしれません。
「自制心や社会性、常識」を身につけている途中の子供に、
「大人の普通」は通用するでしょうか?
同じ過去に生きていない子ども達へ、
「自分たちの頃」をもの差しにして何の意味があるでしょうか?
情報があふれている中、
吟味するのは至難の業。
それでも、大人のセキュリティで対応するしかありません。
その精度を増すためには、
大人も学び続けなければなりません。
責任は重大です。
必要なソフトの一つが「セキュリティソフト」。
インターネット上には、様々な危険があります。
情報を盗むためのもの、お金を奪い取るもの、
パソコンを壊してしまうもの・・・等々。
それを人の病気になぞらえて「ウィルス」といってますが、
その予防が「セキュリティソフト」。
残念ながら、これは予防。
風邪薬のように対処する薬ではありません。
感染しちゃったら、
最悪修復不可能です。
まあ、パソコンの場合は「総入れ替え」って手もありますが・・・。
インターネットといったら、特別なもののように思われがちですが、
よく考えてみると、背景が違うだけで普段の生活と同じです。
泥棒はいるし、ズルする人はいるし、乱暴な人はいるし・・・。
ネットも日常の生活も大差は無いように思います。
大きな違いといえば、その範囲くらいでしょうか。
さて子ども達は、いろんな体験(情報)を糧として成長していきます。
しかし、自制心や社会性、常識が身についてないという意味では、
「セキュリティソフト」の入っていないパソコンと同じです。
つまり「やられ放題」、「されるがまま」です。
「セキュリティソフト」を身につけてもらうしかありません。
プログラムのインストールが終わるまでは、
大人の「セキュリティソフト」で対応するしかありません。
しかし、大人も万全なものを持っているとは限りません。
油断や慢心からウィルスは侵入してきます。
いわゆる「セキュリティホール」です。
油断大敵です。
大人も常にプログラムを更新していかなければなりません。
「子供の意志を尊重」といっても、
自分を築いている最中。
子供に全く委ねてしまうのは危険です。
それこそ、「ウィルスの仕業」に踊らされているだけかもしれません。
「自制心や社会性、常識」を身につけている途中の子供に、
「大人の普通」は通用するでしょうか?
同じ過去に生きていない子ども達へ、
「自分たちの頃」をもの差しにして何の意味があるでしょうか?
情報があふれている中、
吟味するのは至難の業。
それでも、大人のセキュリティで対応するしかありません。
その精度を増すためには、
大人も学び続けなければなりません。
責任は重大です。