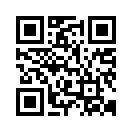› みどり児童館 › 2016年01月
› みどり児童館 › 2016年01月峰禎宏&平田義信
2016年01月26日
一難去って、また一難
昨日は大雪。
雪も溶け、難は去ったかと思いきや、
この寒波の影響で今度は断水。
児童館も出ていません。
保育園も断水の為、
登園を控えるよう言われているようです。
今日は児童館は通常開館。
とりあえずは、生活水。
とりわけ、トイレの水の確保。
児童館で用意したものは、バケツの雪。
・・・でも溶け方がとてもスローリー
間に合うのか!?

間もなく到着したのは、社協事務局から。

そして、役場(住民福祉課)から届けられた非常用の水。

みなさんのおかげで、差し当たってはしのげそうです。
ありがとうございました。
しかし、明日の開館が危ぶまれる事態。
一難去って、また一難。
余波は続いています。
雪も溶け、難は去ったかと思いきや、
この寒波の影響で今度は断水。
児童館も出ていません。
保育園も断水の為、
登園を控えるよう言われているようです。
今日は児童館は通常開館。
とりあえずは、生活水。
とりわけ、トイレの水の確保。
児童館で用意したものは、バケツの雪。
・・・でも溶け方がとてもスローリー
間に合うのか!?

間もなく到着したのは、社協事務局から。

そして、役場(住民福祉課)から届けられた非常用の水。

みなさんのおかげで、差し当たってはしのげそうです。
ありがとうございました。
しかし、明日の開館が危ぶまれる事態。
一難去って、また一難。
余波は続いています。
2016年01月25日
雪や困々(こんこん)
雪や こんこ♪
あられや こんこ♪
などと、悠長に歌ってられなかった今回の大雪。
申年は大荒れ。
そう言った人もいましたが、
いきなりの異常気象。
雪に不慣れな地域では、「立ち往生」続出です。
県下の学校も軒並み臨時休校。
ここ玄海町もご多分に漏れていません。
子どもたちは見慣れない雪景色に、
ハイテンションになっている事でしょう。
おまけに学校はお休みときてるんですから。
本日は学校に準じ、児童館もお休み。
静まりかえった施設の外は断続的な雪。
寂しさを際立たせます。
溶け始めているような気はしますが、
今度は明日の朝の凍結の心配が残ります。
雪だるまをこさえてみたのですが、
こんなに白く作れるのは珍しい。
それにしても、不慣れとは言え、不格好な雪だるまです。
20km走行で、やっとたどり着いた児童館。
辺り一面、風花の乱舞。
車を降りると、そこは雪国だった・・・みたいな・・・

施設の裏も、こんな感じ。

おきまりですが、雪だるま。

再び。真っ白。

玄関前。測ってみると・・・

【追記】
午後5時25分現在。館内気温4.6℃。多分館外、1℃くらい。
だいぶん溶けたようですが、未だちらつく雪。


あられや こんこ♪
などと、悠長に歌ってられなかった今回の大雪。
申年は大荒れ。
そう言った人もいましたが、
いきなりの異常気象。
雪に不慣れな地域では、「立ち往生」続出です。
県下の学校も軒並み臨時休校。
ここ玄海町もご多分に漏れていません。
子どもたちは見慣れない雪景色に、
ハイテンションになっている事でしょう。
おまけに学校はお休みときてるんですから。
本日は学校に準じ、児童館もお休み。
静まりかえった施設の外は断続的な雪。
寂しさを際立たせます。
溶け始めているような気はしますが、
今度は明日の朝の凍結の心配が残ります。
雪だるまをこさえてみたのですが、
こんなに白く作れるのは珍しい。
それにしても、不慣れとは言え、不格好な雪だるまです。
20km走行で、やっとたどり着いた児童館。
辺り一面、風花の乱舞。
車を降りると、そこは雪国だった・・・みたいな・・・

施設の裏も、こんな感じ。

おきまりですが、雪だるま。

再び。真っ白。

玄関前。測ってみると・・・

【追記】
午後5時25分現在。館内気温4.6℃。多分館外、1℃くらい。
だいぶん溶けたようですが、未だちらつく雪。


2016年01月25日
スポーツ鬼ごっこ
児童館では数回行った「スポーツ鬼ごっこ」。
初めての子もいて、少々困惑気味でした。
説明するより、やってみた方が手っ取り早い。
このゲームもその好例。
説明の時、やる気のなさをあらわにしていた子どもも、
やり始めたら、キャッキャッ、キャッキャッ!
時間は5分。先に2勝した方が勝ち。
1試合で終わろうと思っていたのですが、
リクエストによりもう1回。
行事後も、やってみている子どもがいました。
まずは、やってみよう!

作戦タイム!

試合再開!



なお、スポーツ鬼ごっこには、公式HPがありますので、
詳しくは、そちらから。
当児童館では、アレンジを加えています。
初めての子もいて、少々困惑気味でした。
説明するより、やってみた方が手っ取り早い。
このゲームもその好例。
説明の時、やる気のなさをあらわにしていた子どもも、
やり始めたら、キャッキャッ、キャッキャッ!
時間は5分。先に2勝した方が勝ち。
1試合で終わろうと思っていたのですが、
リクエストによりもう1回。
行事後も、やってみている子どもがいました。
まずは、やってみよう!

作戦タイム!

試合再開!



なお、スポーツ鬼ごっこには、公式HPがありますので、
詳しくは、そちらから。
当児童館では、アレンジを加えています。
2016年01月25日
安全教室(地震に備えよう!) ~1月16日~
地震について学びました。
視聴覚教材を元に、
みんなの防災意識を再確認。
まずは、ビデオを観てみましょう。



ビデオが見終わったら、今度はクイズコーナー。



クイズの答えは、お家に持って帰って、
お家の人と再確認できるようにしました。
活用資料:(動画)総務省消防庁「平成20年度 防災学習DVDビデオ『地震だ!その時どうする?』」
(クイズ)有限会社アップルウェザー「防災クイズ ∼ 知ってて よかった ∼」
視聴覚教材を元に、
みんなの防災意識を再確認。
まずは、ビデオを観てみましょう。



ビデオが見終わったら、今度はクイズコーナー。



クイズの答えは、お家に持って帰って、
お家の人と再確認できるようにしました。
活用資料:(動画)総務省消防庁「平成20年度 防災学習DVDビデオ『地震だ!その時どうする?』」
(クイズ)有限会社アップルウェザー「防災クイズ ∼ 知ってて よかった ∼」
2016年01月25日
1月16日の安全教室に寄せて
平成7年1月17日午前5時46分。
忘れてはならない日です。
そう、阪神淡路大震災です。
自分に被害が及ばないと、
つい同じ名前のものは更新してしまいます。
大震災と言えば、「東日本大震災」の人も多いんじゃないでしょうか?
ニュースなどで耳に入り、「関東大震災」も「阪神淡路大震災」も、
「そう言えばあったもの」となってしまってる人もいるかもしれません。
でも一つとして同じ災害はありません。
ひとくくりに出来ない人々の悲しみや苦しみがそこにあります。
決して「上書き保存」にはできません。
それに私たちが暮らしているのは、地震列島・日本です。
「明日は我が身」を忘れてはいけません。
児童館のある玄海町は、地震の珍しい地域です。
だからこそ、ピンとこない災害の一つが地震。
これが東海地方となれば事情が違ってくるのでしょう。
ずいぶん前ですが、三重県の方に旅行した事がありました。
その時に驚いたのが、バスの掲示。
地震の際の対応が書かれているのです。
その時、地震に対する意識の高さに驚いた事を覚えています。
忘れてはならない日です。
そう、阪神淡路大震災です。
自分に被害が及ばないと、
つい同じ名前のものは更新してしまいます。
大震災と言えば、「東日本大震災」の人も多いんじゃないでしょうか?
ニュースなどで耳に入り、「関東大震災」も「阪神淡路大震災」も、
「そう言えばあったもの」となってしまってる人もいるかもしれません。
でも一つとして同じ災害はありません。
ひとくくりに出来ない人々の悲しみや苦しみがそこにあります。
決して「上書き保存」にはできません。
それに私たちが暮らしているのは、地震列島・日本です。
「明日は我が身」を忘れてはいけません。
児童館のある玄海町は、地震の珍しい地域です。
だからこそ、ピンとこない災害の一つが地震。
これが東海地方となれば事情が違ってくるのでしょう。
ずいぶん前ですが、三重県の方に旅行した事がありました。
その時に驚いたのが、バスの掲示。
地震の際の対応が書かれているのです。
その時、地震に対する意識の高さに驚いた事を覚えています。
2016年01月22日
凧を揚げよう! ~1月6日~
次の日で冬休みも終わり。
暖かな松の内。
新年最初の行事は「凧揚げ」。
「お正月」と言えばつきものの遊びです。
児童館の凧は、身近な新聞紙を使った凧です。
絵も描きづらいし、少々地味ですが、
手軽で、よく揚がります。
準備するのは、新聞の見開き1枚。
それに、68センチの竹ひご(直径3ミリ)2本と、適当な長さの凧糸。
詳しくは、「新聞紙、凧」で検索してください。
上半分の所に穴を切り抜くのですが、
その前に少々面倒な(?)折り方があります。
それを間違えると、目的の穴は空きません。
切り取る大きさも大切。
次の難関は、骨(竹ひご)の付け方。
少々曲げてくっつけなければなりません。
何カ所かテープで固定するのですが、
骨のくっつけ方にも注意が必要です。
さてさて、できあがった凧。
子どもたちは、外に出たくて、気がはやります。
風が弱く、ベストコンディションではなかったものの、
うまく風に乗った凧は、グングン空へ駆け上がっていきました。
この凧。
破れやすいのですが、骨さえ折れなければ、
そして新聞紙さえあれば、何度だって作れます。



暖かな松の内。
新年最初の行事は「凧揚げ」。
「お正月」と言えばつきものの遊びです。
児童館の凧は、身近な新聞紙を使った凧です。
絵も描きづらいし、少々地味ですが、
手軽で、よく揚がります。
準備するのは、新聞の見開き1枚。
それに、68センチの竹ひご(直径3ミリ)2本と、適当な長さの凧糸。
詳しくは、「新聞紙、凧」で検索してください。
上半分の所に穴を切り抜くのですが、
その前に少々面倒な(?)折り方があります。
それを間違えると、目的の穴は空きません。
切り取る大きさも大切。
次の難関は、骨(竹ひご)の付け方。
少々曲げてくっつけなければなりません。
何カ所かテープで固定するのですが、
骨のくっつけ方にも注意が必要です。
さてさて、できあがった凧。
子どもたちは、外に出たくて、気がはやります。
風が弱く、ベストコンディションではなかったものの、
うまく風に乗った凧は、グングン空へ駆け上がっていきました。
この凧。
破れやすいのですが、骨さえ折れなければ、
そして新聞紙さえあれば、何度だって作れます。



2016年01月06日
クリスマスケーキ作り ~12月25日~
年末恒例となった「クリスマスケーキ作り」。
材料に限りがあり、定員は30名。
参加できなかった人たちには、
毎度の事ながら、ごめんなさい。
今年は町内のパン屋さん(カウベルンさん)に生地をお願いし、
おいしいケーキを作る事が出来ました。
ケーキ作りは午後からでしたが、
缶詰のフルーツや飾り付け用のスナックの小分け、
会場への机運びなど、
午前中から協力して準備をしました。
いよいよ、ケーキ作り。
まずはホイップクリーム作り。
フンワリ仕立てる、難しいけれど大事な作業。
できあがったクリームを塗ったら、
フルーツやスナックの飾り付け。
今年も楽しいケーキが並びました。
お父さんやお母さんも参加され、
お手伝いもしていただきました。
本当にありがとうございました。





【今年の作品】
材料に限りがあり、定員は30名。
参加できなかった人たちには、
毎度の事ながら、ごめんなさい。
今年は町内のパン屋さん(カウベルンさん)に生地をお願いし、
おいしいケーキを作る事が出来ました。
ケーキ作りは午後からでしたが、
缶詰のフルーツや飾り付け用のスナックの小分け、
会場への机運びなど、
午前中から協力して準備をしました。
いよいよ、ケーキ作り。
まずはホイップクリーム作り。
フンワリ仕立てる、難しいけれど大事な作業。
できあがったクリームを塗ったら、
フルーツやスナックの飾り付け。
今年も楽しいケーキが並びました。
お父さんやお母さんも参加され、
お手伝いもしていただきました。
本当にありがとうございました。





【今年の作品】
2016年01月06日
ハンドベースボール ~12月19日~
ハンドベースボール。
ボールの投げと受け、そして打つタイミング。
おまけにチームの連携。
更には少々細かなルール。
初めての子にとっては、難しかったかもしれません。
途中雨も落ちてきたので、
今回はさわり程度。
どんなものかを感じてもらうだけにしました。
それでも、徐々に熱を帯び、それなりに楽しめるまでになったようです。
行事の後、雨上がりの館庭。
ハンドベースをしようとしていたグループがいました。
企画側としては、嬉しい光景です。



ボールの投げと受け、そして打つタイミング。
おまけにチームの連携。
更には少々細かなルール。
初めての子にとっては、難しかったかもしれません。
途中雨も落ちてきたので、
今回はさわり程度。
どんなものかを感じてもらうだけにしました。
それでも、徐々に熱を帯び、それなりに楽しめるまでになったようです。
行事の後、雨上がりの館庭。
ハンドベースをしようとしていたグループがいました。
企画側としては、嬉しい光景です。



2016年01月06日
クリスマスリース ~12月12日~
間もなくクリスマス。
それにちなんだ、クリスマスリース作り。
リースは、「新年の幸運を祈る」おまじないとも言われています。
トイレットペーパーの芯の部分を組み合わせ、
様々にデコっていきます。
よい年が迎えられますように。





それにちなんだ、クリスマスリース作り。
リースは、「新年の幸運を祈る」おまじないとも言われています。
トイレットペーパーの芯の部分を組み合わせ、
様々にデコっていきます。
よい年が迎えられますように。





2016年01月06日
インフルエンザ(安全教室) ~12月6日~
シーズン突入!
まだ流行は訪れていないものの、インフルエンザのシーズン。
児童館では、これまで「火災」「震災」「風水害」「不審者」「交通」など、
子どもたちの命に危険を及ぼすものについて、学ぶ時間を設けてきました。
その時間が「安全教室」です。
そして、「感染症」もそのひとつ。
分けてもインフルエンザは怖いものの一つ。
怖さを学び、備える大切さを実感することが、対策の根本。
「風邪とインフルエンザの違い」「感染とは何か」「予防方法」など、
どうしても具だくさんになってしまいます。
でも、どれも不可欠な情報です。
それだけ厄介な相手です。
学んだ事をしっかり頭に入れて、
少しでも危険から遠ざかってほしいです。
まずは、うがい、手洗い、マイハンカチ。




まだ流行は訪れていないものの、インフルエンザのシーズン。
児童館では、これまで「火災」「震災」「風水害」「不審者」「交通」など、
子どもたちの命に危険を及ぼすものについて、学ぶ時間を設けてきました。
その時間が「安全教室」です。
そして、「感染症」もそのひとつ。
分けてもインフルエンザは怖いものの一つ。
怖さを学び、備える大切さを実感することが、対策の根本。
「風邪とインフルエンザの違い」「感染とは何か」「予防方法」など、
どうしても具だくさんになってしまいます。
でも、どれも不可欠な情報です。
それだけ厄介な相手です。
学んだ事をしっかり頭に入れて、
少しでも危険から遠ざかってほしいです。
まずは、うがい、手洗い、マイハンカチ。