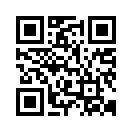› みどり児童館 › 2016年01月22日
› みどり児童館 › 2016年01月22日峰禎宏&平田義信
2016年01月22日
凧を揚げよう! ~1月6日~
次の日で冬休みも終わり。
暖かな松の内。
新年最初の行事は「凧揚げ」。
「お正月」と言えばつきものの遊びです。
児童館の凧は、身近な新聞紙を使った凧です。
絵も描きづらいし、少々地味ですが、
手軽で、よく揚がります。
準備するのは、新聞の見開き1枚。
それに、68センチの竹ひご(直径3ミリ)2本と、適当な長さの凧糸。
詳しくは、「新聞紙、凧」で検索してください。
上半分の所に穴を切り抜くのですが、
その前に少々面倒な(?)折り方があります。
それを間違えると、目的の穴は空きません。
切り取る大きさも大切。
次の難関は、骨(竹ひご)の付け方。
少々曲げてくっつけなければなりません。
何カ所かテープで固定するのですが、
骨のくっつけ方にも注意が必要です。
さてさて、できあがった凧。
子どもたちは、外に出たくて、気がはやります。
風が弱く、ベストコンディションではなかったものの、
うまく風に乗った凧は、グングン空へ駆け上がっていきました。
この凧。
破れやすいのですが、骨さえ折れなければ、
そして新聞紙さえあれば、何度だって作れます。



暖かな松の内。
新年最初の行事は「凧揚げ」。
「お正月」と言えばつきものの遊びです。
児童館の凧は、身近な新聞紙を使った凧です。
絵も描きづらいし、少々地味ですが、
手軽で、よく揚がります。
準備するのは、新聞の見開き1枚。
それに、68センチの竹ひご(直径3ミリ)2本と、適当な長さの凧糸。
詳しくは、「新聞紙、凧」で検索してください。
上半分の所に穴を切り抜くのですが、
その前に少々面倒な(?)折り方があります。
それを間違えると、目的の穴は空きません。
切り取る大きさも大切。
次の難関は、骨(竹ひご)の付け方。
少々曲げてくっつけなければなりません。
何カ所かテープで固定するのですが、
骨のくっつけ方にも注意が必要です。
さてさて、できあがった凧。
子どもたちは、外に出たくて、気がはやります。
風が弱く、ベストコンディションではなかったものの、
うまく風に乗った凧は、グングン空へ駆け上がっていきました。
この凧。
破れやすいのですが、骨さえ折れなければ、
そして新聞紙さえあれば、何度だって作れます。