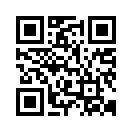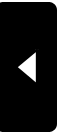› みどり児童館 › 事務室日記
› みどり児童館 › 事務室日記峰禎宏&平田義信
2014年03月07日
6つのめあて
「つるし飾り」の際、子ども達に「6つのめあて」を示しました。
活動の際にはこのことを意識して指導できればと思います。
①「今すること」を考えよう
②自分だけ楽しまない
③比べるのはやめよう
④人と違ったことを
⑤良いことは真似しよう
⑥真似されよう
読み替えれば・・・
①時と場合で行動しよう
②自分勝手は「はた迷惑」
③自分にも友だちにも大事なことは、
~楽しさ一番、「うまい」は最後。~
④発見や発明を見つけよう
⑤周りはみんな先生です
⑥真似は「盗まれたこと」ではなく、教えてあげた証拠
(その人の先生になった証拠)
活動の際にはこのことを意識して指導できればと思います。
①「今すること」を考えよう
②自分だけ楽しまない
③比べるのはやめよう
④人と違ったことを
⑤良いことは真似しよう
⑥真似されよう
読み替えれば・・・
①時と場合で行動しよう
②自分勝手は「はた迷惑」
③自分にも友だちにも大事なことは、
~楽しさ一番、「うまい」は最後。~
④発見や発明を見つけよう
⑤周りはみんな先生です
⑥真似は「盗まれたこと」ではなく、教えてあげた証拠
(その人の先生になった証拠)
2013年12月21日
「おしゃれ」と「身だしなみ」
「おしゃれ」と「身だしなみ」。
どう違うの?
自分を表現する方法として、
服装は一つの手段です。
そこで出てくるのが、この二つの表現。
家で、しかも鏡の前で何を着ようが、
それは自分の勝手。
着ていなくても勝手。
自分の嗜好で自由にできる。
自分が「かっこいい」「かわいい」と思えば、
おしゃれですよね。
しかし一歩外に出たら、
他人の気持ちや行動に影響を与えてしまいます。
自分勝手って訳にはいかなくなります。
場合によっては、
法律で禁じられます。
お葬式に派手なドレス。
海パンや水着だらけの国会。
仮装パーティのような教室。
所構わず「おしゃれ」にしたら、
変な世界になってしまいます。
もう「おしゃれ」とは違う次元かも知れませんね。
そこで出るのが「身だしなみ」。
場を乱さず、
人に不快な思いをさせない。
あくまで周囲に配慮した服装。
そこでは許される範囲の自分勝手しか許されません。
その範囲を見極めるのが、
「おしゃれ」の「センス」かもしれません。
社会人とは、
社会に貢献し、
社会(他人)に配慮できる人を指すものと思います。
社会人として育まれるべき子ども達。
「身だしなみ」を習得させるのも
重要なことだと思います。
仕事をするに当たっては、
信頼を得るための条件でもあります。
学生の頃、
髪の型や色までやかましく言われなければならなかったのか。
個性として何で許してもらえなかったのか。
反発心を持った記憶があります。
「人権として認められるべきではないか」とまでは考えつきませんでしたが・・・。
しかし、社会人として、「公」と「私」を学ぶためには、
必要なことだったように思います。
私も未だに「身だしなみ」を誤ることがあります。
ついつい、機能性や自分の趣向で、
「身だしなみ」の配慮を怠ることがあります。
その度に恥ずかしい思いをするのは自業自得。
・・・悲しいかな、大人ですから・・・。
許された範囲でのみできる「おしゃれ」と、
社会の基本となる「身だしなみ」の区別は、
社会人として留意すべき事には違いないと思います。
たまにはその事について、
ご家庭で話し合われ、
意識する時間を持たれてはいかがでしょうか?
どう違うの?
自分を表現する方法として、
服装は一つの手段です。
そこで出てくるのが、この二つの表現。
家で、しかも鏡の前で何を着ようが、
それは自分の勝手。
着ていなくても勝手。
自分の嗜好で自由にできる。
自分が「かっこいい」「かわいい」と思えば、
おしゃれですよね。
しかし一歩外に出たら、
他人の気持ちや行動に影響を与えてしまいます。
自分勝手って訳にはいかなくなります。
場合によっては、
法律で禁じられます。
お葬式に派手なドレス。
海パンや水着だらけの国会。
仮装パーティのような教室。
所構わず「おしゃれ」にしたら、
変な世界になってしまいます。
もう「おしゃれ」とは違う次元かも知れませんね。
そこで出るのが「身だしなみ」。
場を乱さず、
人に不快な思いをさせない。
あくまで周囲に配慮した服装。
そこでは許される範囲の自分勝手しか許されません。
その範囲を見極めるのが、
「おしゃれ」の「センス」かもしれません。
社会人とは、
社会に貢献し、
社会(他人)に配慮できる人を指すものと思います。
社会人として育まれるべき子ども達。
「身だしなみ」を習得させるのも
重要なことだと思います。
仕事をするに当たっては、
信頼を得るための条件でもあります。
学生の頃、
髪の型や色までやかましく言われなければならなかったのか。
個性として何で許してもらえなかったのか。
反発心を持った記憶があります。
「人権として認められるべきではないか」とまでは考えつきませんでしたが・・・。
しかし、社会人として、「公」と「私」を学ぶためには、
必要なことだったように思います。
私も未だに「身だしなみ」を誤ることがあります。
ついつい、機能性や自分の趣向で、
「身だしなみ」の配慮を怠ることがあります。
その度に恥ずかしい思いをするのは自業自得。
・・・悲しいかな、大人ですから・・・。
許された範囲でのみできる「おしゃれ」と、
社会の基本となる「身だしなみ」の区別は、
社会人として留意すべき事には違いないと思います。
たまにはその事について、
ご家庭で話し合われ、
意識する時間を持たれてはいかがでしょうか?
2013年12月12日
子どもの目線で
「子どもの目線で」
子どもと接する場合によく使われている言葉です。
「相手の立場に立って」の子供版というところでしょうか。
児童館で時々あることですが、
子どもが何処のことを言っているのか
分からないときがあります。
そんなとき、
話を良く聞いて、
子どもの言う角度や高さで見てみると、
分かることがあります。
確かに「子どもの目線で」は大切だと痛感します。
でもそれだけではありません。
その目線をキープすると、
日頃気づかなかったものが見えてくることもあります。
危ないもの、面白いもの、変なものなど。
そこからいろんなことを推定できたりもします。
それは子どもと接する上で、
大人にとって大切な事だと思います。
一方、子どもは大人より小さく、
足下に視線が近いため、
条件的に足下の危険に気づきやすい。
大人にとっては自分の身を守るためにも、
「足下をすくわれない」ためにも、
「子どもの目線で」は大事なことのようです。
足下を心と置き換えたなら、
「子どもの目線で」の方が、
人本来の心に近いかも知れません。
隠れてしまった本心や、
頭と心の行き違いに気づくためには、
これもまた無視できないこと。
とかく大人になると、
体は元より、
習得した常識や知識などで目線が足下から遠のいてしまいます。
おまけに靴底はプライドで厚くなっていきます。
そう考えると、
謙虚に「子どもの目線で」見るということは、
とても意味のあることのように感じます。
「子どもの目線で」は、
弱者に対する態度だけでなく、
自分を知り、他人を知る手段のひとつかもしれません。
危機管理としても十分意味があります。
まさに、「情けは人のためならず」。
「弱いは強い」
「小さいは大きい」
職員であることを除いても、
児童館はいろんなことが学べる場所です。
子どもと接する場合によく使われている言葉です。
「相手の立場に立って」の子供版というところでしょうか。
児童館で時々あることですが、
子どもが何処のことを言っているのか
分からないときがあります。
そんなとき、
話を良く聞いて、
子どもの言う角度や高さで見てみると、
分かることがあります。
確かに「子どもの目線で」は大切だと痛感します。
でもそれだけではありません。
その目線をキープすると、
日頃気づかなかったものが見えてくることもあります。
危ないもの、面白いもの、変なものなど。
そこからいろんなことを推定できたりもします。
それは子どもと接する上で、
大人にとって大切な事だと思います。
一方、子どもは大人より小さく、
足下に視線が近いため、
条件的に足下の危険に気づきやすい。
大人にとっては自分の身を守るためにも、
「足下をすくわれない」ためにも、
「子どもの目線で」は大事なことのようです。
足下を心と置き換えたなら、
「子どもの目線で」の方が、
人本来の心に近いかも知れません。
隠れてしまった本心や、
頭と心の行き違いに気づくためには、
これもまた無視できないこと。
とかく大人になると、
体は元より、
習得した常識や知識などで目線が足下から遠のいてしまいます。
おまけに靴底はプライドで厚くなっていきます。
そう考えると、
謙虚に「子どもの目線で」見るということは、
とても意味のあることのように感じます。
「子どもの目線で」は、
弱者に対する態度だけでなく、
自分を知り、他人を知る手段のひとつかもしれません。
危機管理としても十分意味があります。
まさに、「情けは人のためならず」。
「弱いは強い」
「小さいは大きい」
職員であることを除いても、
児童館はいろんなことが学べる場所です。
2013年10月17日
心のお料理
動機を聞いてみると間違っていないのに、
友だちに嫌な思いをさせてしまう。
間違ったことをしてしまう。
児童館の日常によくあることです。
そんな時、
お料理と似ているなあ、と感じてしまいます。
良い材料を使ったからと言って、
美味しいお料理に仕上がるとは限りません。
量や時間、火加減などで台無しにしてしまうことだってあります。
人に食べさせるものであろうが、
自分で食べるものであろうが同じです。
良い思いつきで行ったからと言って、
人を幸せにするとは限りません。
言葉遣いや行動、関わりの強さなどで
台無しにしてしまうことだってあります。
人も傷つけてしまうし、
自分も傷つけることになってしまいます。
それに両方とも、
そこにいる人、食べる人の立場で行うこと。
これが前提にないと、
駄目なような気がします。
「料理は愛情」なんて言いますよね。
子ども達は良い材料を
たくさん持っています。
そのお料理の仕方は、
友だちや周りの大人達から学びます。
子ども達が、
折角の心を台無しにしないよう、
心を美味しくお料理できるよう、
私達大人にできること。
なかなか難しい課題ですが、
とても大事なことだと思います。
一方、駄目な材料でも、
お料理の仕方によっては・・・。
それは複雑になりますので、
ここでは触れずにおきますね(笑)。
友だちに嫌な思いをさせてしまう。
間違ったことをしてしまう。
児童館の日常によくあることです。
そんな時、
お料理と似ているなあ、と感じてしまいます。
良い材料を使ったからと言って、
美味しいお料理に仕上がるとは限りません。
量や時間、火加減などで台無しにしてしまうことだってあります。
人に食べさせるものであろうが、
自分で食べるものであろうが同じです。
良い思いつきで行ったからと言って、
人を幸せにするとは限りません。
言葉遣いや行動、関わりの強さなどで
台無しにしてしまうことだってあります。
人も傷つけてしまうし、
自分も傷つけることになってしまいます。
それに両方とも、
そこにいる人、食べる人の立場で行うこと。
これが前提にないと、
駄目なような気がします。
「料理は愛情」なんて言いますよね。
子ども達は良い材料を
たくさん持っています。
そのお料理の仕方は、
友だちや周りの大人達から学びます。
子ども達が、
折角の心を台無しにしないよう、
心を美味しくお料理できるよう、
私達大人にできること。
なかなか難しい課題ですが、
とても大事なことだと思います。
一方、駄目な材料でも、
お料理の仕方によっては・・・。
それは複雑になりますので、
ここでは触れずにおきますね(笑)。
2012年10月20日
子どもを育てる10か条
インターネットで
「子育・地域」で検索していたところ、
北九州市のホームページで、
面白いものを見つけました。
「北九州市 子どもを育てる10か条」
~子育て親育ちのための「北九州市 子どもを育てる10か条」~
➀朝は明るく笑顔で「おはよう」
②家族にも「ありがとう」と「ごめんなさい」
③子育ては 誉める・叱る・見守る・抱きしめる
④聞く時は 子どもの目を見て 心を聴いて
⑤食事が楽しみな家庭にしよう
⑥大切にしたい 物より体験
⑦まず親が きちんと実行 社会のルール
⑧声かけて 地域の宝 子どもたち
⑨教えよう 平和といのちと助け合い
⑩子どもと夢を語り合おう
ページには、
それぞれのご家庭で、
もう1箇条定めることを奨励していました。
改めて大事なことと感じました。
この10箇条。
実践できれば素晴らしいことですね。
「子育・地域」で検索していたところ、
北九州市のホームページで、
面白いものを見つけました。
「北九州市 子どもを育てる10か条」
~子育て親育ちのための「北九州市 子どもを育てる10か条」~
➀朝は明るく笑顔で「おはよう」
②家族にも「ありがとう」と「ごめんなさい」
③子育ては 誉める・叱る・見守る・抱きしめる
④聞く時は 子どもの目を見て 心を聴いて
⑤食事が楽しみな家庭にしよう
⑥大切にしたい 物より体験
⑦まず親が きちんと実行 社会のルール
⑧声かけて 地域の宝 子どもたち
⑨教えよう 平和といのちと助け合い
⑩子どもと夢を語り合おう
ページには、
それぞれのご家庭で、
もう1箇条定めることを奨励していました。
改めて大事なことと感じました。
この10箇条。
実践できれば素晴らしいことですね。
2012年10月13日
「言葉」と「言葉遣い」
「言葉」と「言葉遣い」。
同じ意味で使われることがありますが、
その事が多くの誤解を生んでいるように感じます。
丁寧な言葉を使えば、
良い言葉遣いをしてると思われているようですが、
それは違うようです。
返って、
丁寧な言葉を遣うことで、
傷が深まる場合だってあります。
逆に、
言葉自体に汚い響きがあっても、
用い方で癒やす事だってできます。
良い言葉遣いとは、
人に優しい言葉の用い方。
「文は人なり」と言いますが、
言葉遣いもまた、その人そのもの。
子供達には、
「優しい人」と見られる言葉遣いを
身につけて欲しいものです。
反省会の折、それに触れた話をしました。
もちろん、私自身にも言い聞かせながら。
同じ意味で使われることがありますが、
その事が多くの誤解を生んでいるように感じます。
丁寧な言葉を使えば、
良い言葉遣いをしてると思われているようですが、
それは違うようです。
返って、
丁寧な言葉を遣うことで、
傷が深まる場合だってあります。
逆に、
言葉自体に汚い響きがあっても、
用い方で癒やす事だってできます。
良い言葉遣いとは、
人に優しい言葉の用い方。
「文は人なり」と言いますが、
言葉遣いもまた、その人そのもの。
子供達には、
「優しい人」と見られる言葉遣いを
身につけて欲しいものです。
反省会の折、それに触れた話をしました。
もちろん、私自身にも言い聞かせながら。
2012年08月06日
2012年06月23日
ある言葉について
安全教室(6月23日)のあった日、
子供達の会話で、
気にある事がありました。
身体障がい者のことを示す「シンショウ」という言葉。
人として口にしてはいけない言葉。
子供達の間で前に耳にして、
不愉快に思っていたのですが、
寂しい事に、ここでも耳にする事になりました。
改めて子供達に、自分なりの言葉で話しました。
私の怒りの訳を話しました。
もしかしたら、失礼な部分に触れたかも知れません。
その点は、無知故とご容赦ください。
使い方を見ていると、
「バカ」とか「アホ」とかと同じように、
軽い「からかい」の言葉のようです。
まだまだ、その言葉の卑劣さに気づいていないようです。
同和教育の大事さを改めて感じました。
私もどこかで、軽んじているところが
あるかもしれません。
薄っぺらな怒りかも知れません。
辛抱強く、その酷さを教え、
同時に我が身も省みなければと思いました。
子供達の会話で、
気にある事がありました。
身体障がい者のことを示す「シンショウ」という言葉。
人として口にしてはいけない言葉。
子供達の間で前に耳にして、
不愉快に思っていたのですが、
寂しい事に、ここでも耳にする事になりました。
改めて子供達に、自分なりの言葉で話しました。
私の怒りの訳を話しました。
もしかしたら、失礼な部分に触れたかも知れません。
その点は、無知故とご容赦ください。
使い方を見ていると、
「バカ」とか「アホ」とかと同じように、
軽い「からかい」の言葉のようです。
まだまだ、その言葉の卑劣さに気づいていないようです。
同和教育の大事さを改めて感じました。
私もどこかで、軽んじているところが
あるかもしれません。
薄っぺらな怒りかも知れません。
辛抱強く、その酷さを教え、
同時に我が身も省みなければと思いました。
2012年05月28日
お花見
児童館の周辺の植物は、
もちろん、畑ばかりではありません。
花壇や道ばたの草花は、
季節折々の彩りで、
気持ちに安らぎを与えてくれます。
【児童館の草花たち】
スイバをご存じですか?
里や山野を問わず、
そこここに自生している植物です。
私が子供だったウン十年前。
野山を駆け回って、喉が渇いたら、
その草の茎の酸っぱさで唾液を出し、
間に合わせに使いました。
食べ方はサトウキビのように
「かじってチューチュー」です。
調べると、シュウ酸が入っているため、
食べ過ぎは肝臓障害につながるそうです。
今のところ大丈夫なので、
私は食べ過ぎてはいなかったようです。
薬効もあるようですので、
興味のある方はウィキペディアででも。
因みに「スカンポ」とも言うそうです。
私は「シイカンボ」と言ってましたが。
【スイバ】
もちろん、畑ばかりではありません。
花壇や道ばたの草花は、
季節折々の彩りで、
気持ちに安らぎを与えてくれます。
【児童館の草花たち】
スイバをご存じですか?
里や山野を問わず、
そこここに自生している植物です。
私が子供だったウン十年前。
野山を駆け回って、喉が渇いたら、
その草の茎の酸っぱさで唾液を出し、
間に合わせに使いました。
食べ方はサトウキビのように
「かじってチューチュー」です。
調べると、シュウ酸が入っているため、
食べ過ぎは肝臓障害につながるそうです。
今のところ大丈夫なので、
私は食べ過ぎてはいなかったようです。
薬効もあるようですので、
興味のある方はウィキペディアででも。
因みに「スカンポ」とも言うそうです。
私は「シイカンボ」と言ってましたが。
【スイバ】
2012年03月10日
インフルエンザ襲来?!
今日から有徳小学校の一年生は、
学級閉鎖期間に入りました。
先月は値賀小中学校で猛威をふるったインフルエンザ。
有徳小学校はよそ事でした。
胸騒ぎの3月。
ヤツはやはり
時間差攻撃でやって来ました。
子供の話に寄れば、
インフルエンザの出てない学年は5年生だけ、とか。
このまま収束してくれる事を祈るばかりです。
もうすぐ卒業式なのに・・・。
その影響なのか、
今日の来館者は10人を切りました。
予定していた「みどり集会」は、
延期となりました。
学級閉鎖期間に入りました。
先月は値賀小中学校で猛威をふるったインフルエンザ。
有徳小学校はよそ事でした。
胸騒ぎの3月。
ヤツはやはり
時間差攻撃でやって来ました。
子供の話に寄れば、
インフルエンザの出てない学年は5年生だけ、とか。
このまま収束してくれる事を祈るばかりです。
もうすぐ卒業式なのに・・・。
その影響なのか、
今日の来館者は10人を切りました。
予定していた「みどり集会」は、
延期となりました。
2012年03月08日
視察研修 ~福岡市立中央児童会館~
3月7日。
佐賀県児童館連絡協議会の企画で、
福岡市立中央児童会館への視察研修が行われました。
当館からは青木が参加し、
その設備と運営に一言、
すごいっ!


街の真ん中という事もあり、
屋外活動は建物の工夫によって行われていました。
また、何より素晴らしいのは、
ボランティアの登録制度によって、
市民参加の児童育成を図られ、
地域の取り組みとして機能しているところです。
更には、いくつかのクラブ活動が行われ、
子供のカルチャーセンターの役目も担っており、
施設の有効な活用を実践されていました。

地域性、地域の規模などもあり、
全てを参考とするわけにはいきませんが、
こういった研修を重ね、
当館のより有意義な運営の糧にしていきたいと思います。
そしてこれからも、
皆さんにとって、
地域と子育ての関わりを考える機会となりますよう、
こうした研修の内容をお知らせできればと思います。
【研修_福岡市立中央児童会館】
佐賀県児童館連絡協議会の企画で、
福岡市立中央児童会館への視察研修が行われました。
当館からは青木が参加し、
その設備と運営に一言、
すごいっ!


街の真ん中という事もあり、
屋外活動は建物の工夫によって行われていました。
また、何より素晴らしいのは、
ボランティアの登録制度によって、
市民参加の児童育成を図られ、
地域の取り組みとして機能しているところです。
更には、いくつかのクラブ活動が行われ、
子供のカルチャーセンターの役目も担っており、
施設の有効な活用を実践されていました。

地域性、地域の規模などもあり、
全てを参考とするわけにはいきませんが、
こういった研修を重ね、
当館のより有意義な運営の糧にしていきたいと思います。
そしてこれからも、
皆さんにとって、
地域と子育ての関わりを考える機会となりますよう、
こうした研修の内容をお知らせできればと思います。
【研修_福岡市立中央児童会館】
2011年03月12日
東北地方太平洋沖地震によせて
北海道、東北並びに北関東地方にて被災された皆さん、
お見舞いを申し上げます。
また、不幸にもお亡くなりになった皆さん、
衷心よりご冥福をお祈りいたします。
テレビに映し出される、目を疑うほどの光景。
心身ともに襲った、その衝撃的な惨事は、
私たちの想像など遙かに及ばぬものと思います。
ブログにはいろんな方がお見えになります。
もしかすると、被災された何方かがいらっしゃるかもしれません。
児童館にやってくるような子供たちが、
どこかの避難所で、不安の夜に眠っているのかもしれません。
そう思うと、私たちにとって決して他人事とはならないのです。
朝夕の冷え込みはまだまだ厳しいようです。
どうぞ、お体に気をつけてください。
ご不自由でしょうが、
どうぞ、ご無事でいてください。
皆さんに一刻も早く「日常」と「安らかな眠り」が戻ってきますよう、
心からお祈り申し上げます。
とりわけ子供たちに、一刻も早く笑顔が戻ってきますように。
お見舞いを申し上げます。
また、不幸にもお亡くなりになった皆さん、
衷心よりご冥福をお祈りいたします。
テレビに映し出される、目を疑うほどの光景。
心身ともに襲った、その衝撃的な惨事は、
私たちの想像など遙かに及ばぬものと思います。
ブログにはいろんな方がお見えになります。
もしかすると、被災された何方かがいらっしゃるかもしれません。
児童館にやってくるような子供たちが、
どこかの避難所で、不安の夜に眠っているのかもしれません。
そう思うと、私たちにとって決して他人事とはならないのです。
朝夕の冷え込みはまだまだ厳しいようです。
どうぞ、お体に気をつけてください。
ご不自由でしょうが、
どうぞ、ご無事でいてください。
皆さんに一刻も早く「日常」と「安らかな眠り」が戻ってきますよう、
心からお祈り申し上げます。
とりわけ子供たちに、一刻も早く笑顔が戻ってきますように。
2011年02月23日
手話教室を終えて
音のない世界。
聞こえて当たり前の私たち。
きっと想像しても到底及ばない世界なのでしょう。
人と会話をするには共通の言葉が必要です。
それが声であったり、身振り手振りであったり、
表情であったり。
世の中にはいろんな人がいます。
国が違う人。
地域が違う人。
年齢が違う人。
性別が違う人。
好みが違う人。
その他いろいろ違う人。
でもお互いが理解しようとする気持ちがあれば、
通じることも多いはず。
目の見えない人、
耳の聞こえない人も同じなのかもしれません。
共通の言葉としての手話。
それを知ることは、
出会いを増やす手段の一つです。
耳が聞こえないというだけで、
無縁の人を作ってしまうのは、
とても不幸なことです。
自分と違うと言うだけで、
その人のすばらしさを避けてしまうのはもったいない。
今回の手話教室が、
子どもたちにもっと沢山の出会いのチャンスをもたらしてくれたら幸せです。
最後に、手話を教えてくださった杉山さんに、こんな質問を投げかけました。
「耳が聞こえないと言うことで、怖いことは何ですか?」
「車の音が聞こえない」とか、「踏切」とか、そんな答えが返ってくると思ってました。
しかし、返ってきた答えはこうでした。
「いじめられることです。」
杉山さんが、そう答えなくてすむ世の中を築いていきたいですね。
聞こえて当たり前の私たち。
きっと想像しても到底及ばない世界なのでしょう。
人と会話をするには共通の言葉が必要です。
それが声であったり、身振り手振りであったり、
表情であったり。
世の中にはいろんな人がいます。
国が違う人。
地域が違う人。
年齢が違う人。
性別が違う人。
好みが違う人。
その他いろいろ違う人。
でもお互いが理解しようとする気持ちがあれば、
通じることも多いはず。
目の見えない人、
耳の聞こえない人も同じなのかもしれません。
共通の言葉としての手話。
それを知ることは、
出会いを増やす手段の一つです。
耳が聞こえないというだけで、
無縁の人を作ってしまうのは、
とても不幸なことです。
自分と違うと言うだけで、
その人のすばらしさを避けてしまうのはもったいない。
今回の手話教室が、
子どもたちにもっと沢山の出会いのチャンスをもたらしてくれたら幸せです。
最後に、手話を教えてくださった杉山さんに、こんな質問を投げかけました。
「耳が聞こえないと言うことで、怖いことは何ですか?」
「車の音が聞こえない」とか、「踏切」とか、そんな答えが返ってくると思ってました。
しかし、返ってきた答えはこうでした。
「いじめられることです。」
杉山さんが、そう答えなくてすむ世の中を築いていきたいですね。
2010年12月15日
3ヶ月が過ぎて
みどり児童館が始まって、3ヶ月が過ぎました。
もうすぐ新たな年を迎えようとしています。
日々、改善改善の毎日。
子どもたちにとっては、
「あっ、昨日と言うことが違う!」
と言われてしまうことも少なからずあります。
準備不足な点もありましたが、
歩き出さなければ見えてこない風景もありました。
それに対処している中には、
不満や不審につながることも、
たくさん含まれていたと思います。
その都度説明はしているのですが、
100パーセント納得させるのは難しいです。
子どもたちには、
改悪に映ってしまうこともあったかもしれません。
職員は子どもたちの健全育成を手助けする立場です。
それには、指導する場面もあります。
訓練を促す場合もあります。
そんな中、我慢を強いる場合もあります。
片方では伸び伸びと遊ぼうと言い、
片方では規律を守れと言う。
子どもたちにとっては、
相反することかもしれません。
いろんな心の形を持った子どもたち。
緩急の割合を一様にするには難しい面もあります。
ここにいる子どもたちにとって、
どんな「みどり児童館」になると良いのか。
子どもたちと、
どんな「みどり児童館」を築けるのか。
答えを出すには、もうしばらく時間がかかりそうです。
もうすぐ新たな年を迎えようとしています。
日々、改善改善の毎日。
子どもたちにとっては、
「あっ、昨日と言うことが違う!」
と言われてしまうことも少なからずあります。
準備不足な点もありましたが、
歩き出さなければ見えてこない風景もありました。
それに対処している中には、
不満や不審につながることも、
たくさん含まれていたと思います。
その都度説明はしているのですが、
100パーセント納得させるのは難しいです。
子どもたちには、
改悪に映ってしまうこともあったかもしれません。
職員は子どもたちの健全育成を手助けする立場です。
それには、指導する場面もあります。
訓練を促す場合もあります。
そんな中、我慢を強いる場合もあります。
片方では伸び伸びと遊ぼうと言い、
片方では規律を守れと言う。
子どもたちにとっては、
相反することかもしれません。
いろんな心の形を持った子どもたち。
緩急の割合を一様にするには難しい面もあります。
ここにいる子どもたちにとって、
どんな「みどり児童館」になると良いのか。
子どもたちと、
どんな「みどり児童館」を築けるのか。
答えを出すには、もうしばらく時間がかかりそうです。
2010年12月02日
頭痛の種
頭を痛めます。
児童クラブから児童館に変わって、継続して使っている子どもたちには不自由を強いている部分があるように感じます。これまでできたことが、急に「できないこと」になったのですから仕方ありません。しかしそれも、かわいそうですがなれてもらわなければなりません。もっとも、活動できる施設も広がり、遊具も増えたのですから、これもまた仕方のないこと。「のびのびと活動してほしい」という気持ちと、実際の運営管理の間で、常に職員が頭を痛めるところです。
差し当たって絞り込むと、頭痛の種は2つ。
まずは、外遊びの範囲。
学校との隣接は、何かと都合の良いところもありますが、管理の区分で難しい面もあります。学校の運動場も、児童館の館庭も常にオープンになっています。児童館の職員体制で、運動場までをカバーするのは大変難しいというのが本音です。かといって敷居を設けると、せっかく使える遊び場を児童館が奪うことになってしまうように感じ、運動場までは出て良いことにしています。子どもたちを信用するしかありません。けれど、ついつい運動場の先へ出て行った子を、連れ戻しに行ったこともしばしば。近くに川も流れています。それも心配。だからといって、心配を取り除いてしまおうとすると、またまた子どもたちの不自由につながってしまう。
そして、遊具の後片付け。
気にかけている子は出来ているようですが、注意をしているにも関わらず、徹底できてません。何度も学校の先生方から、「川に落ちてたよ」「運動場に転がってたよ」と、ボールを届けていただいています。館庭でも、使った子が不明のボールや一輪車などが置き去りにされています。出来るだけ罰則で縛ることはしたくないのですが、そうしないと遊具がなくなってしまう危険すらある場合があります。児童館は町のお金で買っていただいているので、その意味でも申し訳ないです。「物を大事に」ということが、年々教えづらくなっています。児童館での忘れ物でもそれがうかがえます。文具をはじめ、水筒や衣類など、必ずと言っていいほど忘れ物があります。中には、「こんなものまで?」と首をかしげる物も見かけたりします。持ち主が現れれば良い方で、捨てられてしまう物も珍しくありません。
2つの頭痛の種は、おそらく長引くテーマになると思います。
児童クラブから児童館に変わって、継続して使っている子どもたちには不自由を強いている部分があるように感じます。これまでできたことが、急に「できないこと」になったのですから仕方ありません。しかしそれも、かわいそうですがなれてもらわなければなりません。もっとも、活動できる施設も広がり、遊具も増えたのですから、これもまた仕方のないこと。「のびのびと活動してほしい」という気持ちと、実際の運営管理の間で、常に職員が頭を痛めるところです。
差し当たって絞り込むと、頭痛の種は2つ。
まずは、外遊びの範囲。
学校との隣接は、何かと都合の良いところもありますが、管理の区分で難しい面もあります。学校の運動場も、児童館の館庭も常にオープンになっています。児童館の職員体制で、運動場までをカバーするのは大変難しいというのが本音です。かといって敷居を設けると、せっかく使える遊び場を児童館が奪うことになってしまうように感じ、運動場までは出て良いことにしています。子どもたちを信用するしかありません。けれど、ついつい運動場の先へ出て行った子を、連れ戻しに行ったこともしばしば。近くに川も流れています。それも心配。だからといって、心配を取り除いてしまおうとすると、またまた子どもたちの不自由につながってしまう。
そして、遊具の後片付け。
気にかけている子は出来ているようですが、注意をしているにも関わらず、徹底できてません。何度も学校の先生方から、「川に落ちてたよ」「運動場に転がってたよ」と、ボールを届けていただいています。館庭でも、使った子が不明のボールや一輪車などが置き去りにされています。出来るだけ罰則で縛ることはしたくないのですが、そうしないと遊具がなくなってしまう危険すらある場合があります。児童館は町のお金で買っていただいているので、その意味でも申し訳ないです。「物を大事に」ということが、年々教えづらくなっています。児童館での忘れ物でもそれがうかがえます。文具をはじめ、水筒や衣類など、必ずと言っていいほど忘れ物があります。中には、「こんなものまで?」と首をかしげる物も見かけたりします。持ち主が現れれば良い方で、捨てられてしまう物も珍しくありません。
2つの頭痛の種は、おそらく長引くテーマになると思います。
2010年11月29日
秋も深まってまいりました。
秋が冬へと塗り替えられていく今日この頃。朝夕の気温も一桁が珍しくなってきました。
今朝は霜も降りたようです。
子どもたちは・・・・と言うと、オールシーズン元気いっぱいです。
児童館の周りは、農園作りが着々と進んでいます。
二十日大根
ブロッコリー
スナックエンドウ
タマネギ
春菊
小松菜
ネギ
既に芽が出て育ち始めています。
そして、希望としては小麦(・・・春小麦はもう無理かも・・・)
表の畑は準備中。
使っているのは、裏の畑が中心。
裏といえば、児童館には一本の紅葉があります。
なかなか色づかず、あきらめていたのですが、
それなりに色づいてくれたようです。
下のは、うちの専属カメラマン「seiko」の作品です。
表にある忠魂碑の銀杏も激写したようです。


今朝は霜も降りたようです。
子どもたちは・・・・と言うと、オールシーズン元気いっぱいです。
児童館の周りは、農園作りが着々と進んでいます。
二十日大根
ブロッコリー
スナックエンドウ
タマネギ
春菊
小松菜
ネギ
既に芽が出て育ち始めています。
そして、希望としては小麦(・・・春小麦はもう無理かも・・・)
表の畑は準備中。
使っているのは、裏の畑が中心。
裏といえば、児童館には一本の紅葉があります。
なかなか色づかず、あきらめていたのですが、
それなりに色づいてくれたようです。
下のは、うちの専属カメラマン「seiko」の作品です。
表にある忠魂碑の銀杏も激写したようです。


2010年11月15日
日々のつれづれに
ブログは、ご覧の方々に、できるだけ児童館の雰囲気を感じていただき、
できるだけ児童館を知っていただくのが大きな目的です。
しかしながら、ただ目に見える部分だけをご覧いただくだけでは、
お伝えできない実態があるのではないかという不安を感じます。
そこで、日々職員が考えること、感じることを、「事務室日記」という形で、
時折書かせていただきたいと思います。
それを通じて、日頃子どもたちに接している職員も含めて、
「みどり児童館」というものを知っていただけたら幸いです。
※児童館の「事務室」は、学校でいうところの「職員室」とお考えいただいて差し支えありません。
できるだけ児童館を知っていただくのが大きな目的です。
しかしながら、ただ目に見える部分だけをご覧いただくだけでは、
お伝えできない実態があるのではないかという不安を感じます。
そこで、日々職員が考えること、感じることを、「事務室日記」という形で、
時折書かせていただきたいと思います。
それを通じて、日頃子どもたちに接している職員も含めて、
「みどり児童館」というものを知っていただけたら幸いです。
※児童館の「事務室」は、学校でいうところの「職員室」とお考えいただいて差し支えありません。